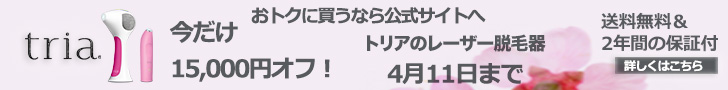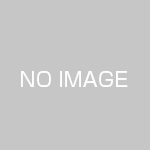『糖質と糖類』ってどう違うの!?あなたは知ってる?美容と健康に役立つ知識☆
糖質と糖類に違いはあるの?
以前は甘いもの=糖分といったように大ざっぱにまとめた言い方をしていた人が多くいましたが、糖質制限ダイエットが流行したあたりから、糖質や糖類という言葉も少しずつ広がりをみせるようになってきました。
普段の会話の中では「糖類」「糖質」という言葉を意識して使い分けている人は少ないと思います。特に「このケーキ糖分多いよね」と言ったように糖分はスムーズに口から出てくるのですが、糖質という言葉はまだ堅苦しさをおぼえる人もいるのでは無いでしょうか?そもそも糖質と糖類に違いはあるのでしょうか?
「糖質」という言葉を調べてみると、炭水化物から食物繊維を引いた、砂糖やブドウ糖、果糖、オリゴ糖など、糖類と呼ばれる糖全般の総称として使うのが正しい使い方のようです。
「糖類」という言葉は、糖質と同じ意味で使われたり、甘い物全般のことだったり、糖の量を表す時に使われたりと、使う人によってまちまちで定義はっきりしていないようなので、会話時の前後の言葉によって意味を判断するしかなさそうです。
栄養表示で糖質を探しても記載されていない?!
糖質のことが気になると、市販されている商品の裏に記載されている栄養表示を確認すると思うのですが、糖質が記載されていないケースがほとんどです。
一般に市販されている商品の栄養表示は健康促進法によって表示されています。栄養素として表示する義務があるのは「カロリー(熱量)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の5つです。
食品1つをとってみても、細かく栄養素を書き出すと数十種類を超えてしまいますので、商品のパッケージに全ての栄養素を記載すると膨大なデータを載せることになってしまいます。
そのような背景もあって栄養表示にはこの5つの表示だけが義務付けられています。そのため糖質は単体で記載されていないことが多いのです。
もちろん、この5つ以上に細かく記載するかどうかはメーカーの自由なのですが、食品を細かく分析する手間もかなり掛かってしまいますので、記載しないメーカーも多いようです。では、私達はどこを見て糖質を知れば良いのでしょうか?
糖質について知るには栄養表示のどの部分を見れば良い?
<不二家 カントリーマアム1枚(11.6g)の栄養成分表>
・熱量56kcal
・たんぱく質0.6g
・脂質2.8g
・炭水化物7.1g
・ナトリウム22mg
カントリーマアムは誰もが知っている甘いクッキーだと思います。しかしこのお菓子の栄養表示には糖質は書かれていません。これを見て「糖質は栄養素として記載されないんだ」と誤解してしまいそうですが実は糖質は記載されています。
では私達はどこで糖質を知れば良いのでしょうか?実は、糖質を見つけるカギは栄養表示の炭水化物の中にあります。炭水化物を辞書で調べると「炭水化物:糖ともいう」と言ったように炭水化物=糖質と表現する場合もあります。市販されている食品の栄養表示の場合には炭水化物の中に糖質が隠れています。
<カルビー ポテトチップス コンソメパンチ60gの栄養成分表>
・熱量(エネルギー)335kcal
・たんぱく質3.0g
・脂質21.1g
・炭水化物33.2g
・ナトリウム215mg
またポテトチップスにも糖質表示はありません。「甘く無いお菓子だから糖質表示が無くても良いのでは・・?」と思ったかもれませんが、糖質はやっぱり炭水化物の中に隠れています。
甘くないお菓子でも糖質が高いケースは案外あるのですが、糖質という言葉で記載されていないので、ついつい見落としがちです。現に、芋が原材料であるポテトチップスにはブドウ糖が多く含まれています。
炭水化物には糖質と食物繊維が含まれている!
食品のパッケージに記載されている炭水化物の多くは、食物繊維+糖質のことです。食物繊維は主に、水分を吸収しながらお腹の中をきれいにしていき、不必要な栄養素を身体の外へ排出する役目があります。
糖質は身体の中でエネルギーになって、脳や筋肉、細胞壁などの栄養源として活用されます。ただし、余ったエネルギーは脂肪として貯金されていきますので、糖質の摂り過ぎは肥満の原因と言われています。
糖質と食物繊維はまったく違う働きをするのに、何故合体させて炭水化物として一緒に表示するのでしょうか?この答えを簡単に言ってしまうと、食物繊維と糖質を分けて表示しなさいという義務が無いからです。
栄養表示じたいも、必ず表示しなさいという法律はありません、ただ栄養表示を載せるなら上記であげた5つの栄養素は表示しましょう。といったルールがあるだけです。
そのため私達が食品にどれくらいの量の糖質が含まれているのかを知りたいと思ったら、栄養表示の炭水化物の部分を見れば良いのですが、炭水化物の中には糖質と食物繊維が含まれていますので、おおよその目安として考えるのが良いかもしれません。
炭水化物(糖質)を多く含む食材として有名なのは、お米や小麦粉で作られた麺類やパン、パスタなどだと思います。炭水化物を単純に糖質だと考えると、甘い食べ物や砂糖ばかり気にしがちですが、、豆製品やアルコール、乳製品、野菜などにも多く含まれています。甘くない食材にも糖質があることを意識しておく必要があるようです。
糖質は主に「単糖類」「小糖類」「多糖類」に分類される
糖質は、果糖やブドウ糖、砂糖、麦芽糖、でんぷん、オリゴ糖などの糖類と呼ばれるもの全般の総称のことを指しています。糖質を更に細かく分類していくと「単糖類」「二糖類」「三糖類」「小糖類」「多糖類」「糖アルコール」といったように細かく分類することが出来ます。
糖の中で一番小さい分子となる単糖類!
これ以上小さくなることが無い単独の分子になった糖を単糖類と呼びます。単糖類にはブドウ糖や果糖、脳糖と呼ばれるものなどがあります。
<単糖類>
・果糖(フルクトース)
・ブドウ糖(グルコース)
・脳糖(ガラクトース)
果糖(フルクトース)は果物に含まれている糖のことで、甘みが強く感じられて、水に溶けやすいという特徴があります。血糖値が上がりにくい糖とも言われていますので空腹の朝一番の時でもおすすめです。
ブドウ糖(グルコース)は果物やハチミツに含まれていて、フルクトース(果糖)とよく似た特徴を持っていますが、分子の構造が違っています。果糖ほど甘さは強くありませんが、すぐにエネルギーとして体内に取り込まれて血糖値を上昇させる特徴があります。
脳糖(ガラクトース)は乳製品などに多く含まれている糖です。脳の発達や細胞の発達に必要な栄養素と言われていて、体内で合成することができます。
二糖類、三糖類、小糖類、多糖類の違いとは?
単糖が2個以上くっついて出来た糖を小糖類と呼びます。単糖が2個くっついたなら二糖類、3個の単糖がくっついたなら三糖類と呼ばれ細かく分類される時もあります。
<小糖類>
・砂糖やショ糖(スクロース)
・乳糖(ラクトース)
・トレハロース
・麦芽糖(マルトース)
砂糖やショ糖(スクロース)は主にサトウキビや甜菜が原材料となっています。ショ糖はブドウ糖と果糖がひっついて出来たものです。私達が普段から料理やコーヒーなどによく使っているのがこの砂糖です。
乳頭(ラクトース)は読んで字のごとく、母乳や凝乳など乳の中に含まれる糖のことです。乳糖は身体の中に取り込まれると腸内の働きを活発にさせますので、お腹を壊してしまう人もいます。
学生の頃はクラスに何人か牛乳や乳製品に弱い人いましたよね。乳糖には善玉菌を増やしたり、免疫力を高めたり、カルシウムの吸収を助けたりと良い面もたくさんあります。
麦芽糖(マルトース)はブドウ糖が2つひっついたもので、ビールに使われる麦芽からとれます。他の糖類に比べるとカロリーが低く、身体への吸収速度もゆっくりなので、ダイエットの時には麦芽糖がおすすめと言われています。
トレハロースは、きのこなどの植物やバッタやハチなどの昆虫、微生物の体内にも存在すると言われている糖です。
トレハロースを体内に取り込んでも、血糖値やインスリンの分泌が穏やかで、血糖値がピークになってからの下がり方もゆっくりなので身体にとても優しいのが特徴です。甘みが少なく、肌にも良い影響があるということで、食品だけでなくスキンケア用品などにも使われている多機能な糖です。
<多糖類とは?>
多糖類にはセルロース、グリコーゲンやでんぷんなどがあります。単糖類や小糖類が味覚としてダイレクトに甘いのに対して、多糖類は味覚の甘さをあまり感じない食品にも多く含まれています。
でんぷんが多く含まれている食品としては、麦や穀物、お米、ジャガイモ、トウモロコシなどです。でんぷんは身体の中に取り込まれるとブドウ糖に変化して、エネルギーとなって活動するのですが、食べる時に甘さを強く感じないので知らず知らずのうちに、たくさんの糖質を摂取してしまうこともあります。
ダイエットと糖の関係は?
糖質は私達のエネルギーとして必ず必要な栄養素なのですが、摂り過ぎて余ってしまうと脂肪になって身体に蓄積されてしまいますので、ダイエット中は特に糖質の摂取量に気を付ける必要があります。
厚生労働省は日本人は一日250g~300gの糖質を摂取しても良いと推奨していますので、普段からこれ以上の糖質量をとっていないか、まずは自分の食事内容を書き出して一度確認してみるようにしましょう。
糖質の摂取量を減らす一番簡単な方法は、一日3回の食事の中の主食の量を減らす、つまり炭水化物を減らすことです。炭水化物=糖と表現されるように炭水化物を糖と考えれば、他の細かいことはいろいろ考えずに糖の摂取量を減らすことが出来ます。
とは言っても、脳は栄養源として糖以外は受け付けませんので、糖質を完全にゼロにするのは、身体に悪い影響が出てしまいます。糖質を全くとらないということはダメなので、まずは毎食お米の量を通常の半分に減らすことから始めてみましょう。
ただしこれだけだと、急激に体重が減少するということはありません、長期間続けていくことを目標に、焦らずじっくりとダイエットに取り組むようにしましょう。
血糖値を意識すると糖質の大切さがわかる!
糖質を考える上でもう一つ気にしなくてはいけないのが「血糖値」についてです。食事をすると血糖値が上がります。急激に血糖値が上がってしまうと、細胞膜が炎症をおこしたり、インスリンの分泌が上手くいかなくなって低血糖になったりと、身体に悪影響が出る可能性があります。
食後に一番血糖値が上がりやすいと言われている糖質は白いお砂糖です。そのため空腹時には、白いお砂糖を使っている食材や飲料水は避けたほうが良いのです。またすぐにエネルギーに変わるごはんやパン、めん類なども、血糖値を急激に上げると言われています。
血糖値が急激に上がると、脂肪を溜めやすい身体になったり、高血圧になるるとも言われていますので、糖質を気にするなら血糖値が急激に上がらない食材を選んで食べていくのがおすすめです。
血糖値を急激に上げない食材とは?
食べ物を食べて、血糖値が全く上がらないというわけにはいきませんが、糖質の種類(トレハロースやマルトース)や食べる食材を意識することで、血糖値の上昇をゆっくりにすることは出来ます。
<血糖値の上昇をゆっくりに出来る食材>
・ごぼうなど糖質の低い野菜全般
・きのこ類
・玄米
・そば
・海藻類など
炭水化物は血糖値がすぐに上がってしまう可能性が高いので、普段の食事の時も、糖質が低い野菜から食べるようにしましょう。きのこ、海藻類、卵、豆乳や豆類、汁物、お魚や肉などを食べてから、主食の炭水化物を食べるようにすれば、血糖値の上昇はゆっくりに抑えることができます。
食事後の血糖値は、通常であれば2時間くらいで元の数値に戻るのですが、成人病や高血圧など身体に不調があると、血糖値が下がりにくい身体になってしまいます。普段の食事で血糖値を意識することは健康な身体作りにも役立ちます。
糖質と糖類のまとめ
糖と一言で言っても、細かく分類していくと数十種類以上あり、分子構造なども違っていて身体の中での働き方にも違いがあります。ダイエットや健康のことを考えると、血糖値が上がりずらい糖質を選ぶのが正解です。
しかしスポーツをする前や筋肉トレーニングの後には、直ぐにエナルギーとして活躍する糖質を選ぶことが効果的です。糖質を身体に良いものとするのか、悪いものとするのかは、その時の状況によって違ってきます。
糖に対して正しい知識をもって状況によって使い分ければ、健康にも美容にも良い作用となって活躍することができますので、明日からは甘い物を「糖分」と一つのくくりにしないで、糖質を状況によって使い分けることをおすすめします。