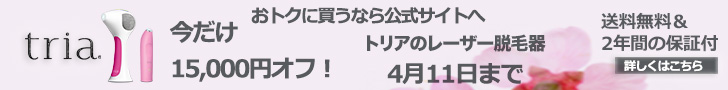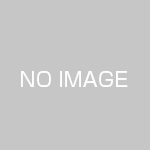胎嚢が確認できるのは妊娠何週目?確認までの3つの流れや確認方法、次期・確認できない4つの理由と体調変化などを紹介します!
妊娠発覚から胎嚢確認まで
妊娠を望まれている女性にとっては、とても喜ばしい妊娠発覚ですが、予定通り月経が来ず、妊娠検査薬で妊娠しているかを確認されるのではないでしょうか。
しかし、胎嚢がちゃんと確認できない時期(妊娠超初期)に妊娠検査薬で陽性反応が出たとしても、妊娠と判断されません。妊娠超初期に妊娠発覚したとしても、あせらずゆったりと過ごし、胎嚢が確認できるまで楽しみに待ちましょう。
今回は、胎嚢についてや胎嚢確認までの流れ、胎嚢の確認時期や確認方法について、胎嚢確認後の流れ、胎嚢が確認できない理由や体調の変化について紹介していきます。初めて妊娠された方、妊娠を希望されている方など、ぜひ参考にしてみてくださいね。
胎嚢とは
赤ちゃんが入っている袋
胎嚢とは、赤ちゃんが入っている袋のことを言います。子宮内膜に受精した卵子が着床し、赤ちゃんを包み込む袋が作られます。
妊娠すると最初にできる
胎嚢は妊娠すると最初にでき、産婦人科などで超音波検査を行い確認します。胎嚢を確認した時点で、妊娠と判断されます。
胎嚢確認までの流れ
妊娠のセルフ判定
妊娠のセルフ判定は妊娠検査薬を使用して妊娠しているかどうかを判断します。妊娠している場合はほぼ陽性反応が出ると言われています。妊娠検査薬は、尿中に含まれているhcgホルモンと呼ばれるヒト絨毛性ゴナドトロピンが含まれているかによって、妊娠の有無を判定されます。一般的に妊娠検査薬は尿中にhcgホルモンが50mlU/ml以上含まれていると陽性反応を示します。
hcgホルモンが50mlU/mlに達するのは、生理予定日の1週間後以降と言われておりますが、場合によっては排卵後14日から生理予定日の間に陽性反応を示す場合があると言われています。確実に妊娠を判定したい場合は、生理予定日の1週間後以降が良いでしょう。
もともと生理周期が不安定な方や、規則正しく生理がくる方でも、その月の生理が遅れている可能性もあるため、早く妊娠が知りたくても生理予定日から1週間以上経ってから検査するのが一般的と言われています。
妊娠検査薬で判定した結果が陰性だった時には、1週間程度生理が来ないか様子を見ましょう。1週間様子を見ても生理が来ない場合にはもう1度判定して、妊娠していないか確かめてみてください。
産婦人科受診
妊娠検査薬で陽性反応が出た場合には、産婦人科を受診したほうが良いでしょう。産婦人科を受診したら、医師が尿検査や超音波検査を行い、妊娠の有無を正確に判断します。妊娠週数によっては胎嚢が確認できない場合がありますので、早すぎる受診は控えたほうが良いです。
大体妊娠して5週目頃から胎嚢の確認ができると言われていますので、明らかな体調不良がない限りは、余裕を持って受診したほうが良いかもしれません。また、妊娠5週目以降で子宮内に胎嚢が確認できない場合には、子宮外妊娠の可能性もあるため、産婦人科の受診を近い間隔で行うようになると言われています。
次回受診日決定
胎嚢が子宮内に確認できたら、通常の妊娠と判断されます。そして、次回の産婦人科の受診日を決められ、次回の診察で胎児の確認と心拍の確認を行うと言われています。
胎嚢の確認ができない場合も、子宮外妊娠などの異常妊娠の可能性もあるため、慎重に診る必要があり、次回の受診は早めに行います。次回の産婦人科受診までは、流産の心配もあるため、どうしても不安になりやすいですが、あまり不安にならないよう普段通り生活してくださいね。
胎嚢の確認時期はいつ頃か
妊娠5週目頃から
胎嚢の確認は妊娠週数5週目頃から確認ができ、6週までには100%確認されると言われています。妊娠週数6週を経過したが、子宮内に胎嚢が確認できない場合には正常な状態とは言えないため、医師の指示を仰ぎましょう。
大きさ・見え方に個人差がある
超音波検査により胎嚢が確認され、妊娠5週目ごろには大きさは5~13mmと言われており、胎嚢の大きさもしくは見え方には個人差があると言われています。しかし、胎嚢が小さくても大きくても、個人差があるものなので、気にする必要はないと言われています。
体外受精の場合
体外受精は不妊症の治療中の方などが行うと言われており、女性の卵巣から成熟した卵子を取り出し、男性の精液の中から元気の良い精子だけを選び洗浄して、卵子と精子を体の外で出会わせて受精することを言います。
体の外で受精させたら、胚盤胞と呼ばれる着床寸前の状態まで発育させ、この胚盤胞を子宮内に戻し、着床して妊娠という流れが、体外受精の流れになります。体外受精が上手くいき、胚盤胞を子宮内に戻してから2週間が経つと、hcgホルモンを確認し着床の有無の診断を行います。そして、着床が上手くいっていれば、さらに1週間後(妊娠5週目)には胎嚢が確認できると言われています。
不妊治療を行っている方にとっては、体外受精は日々気にかけ、根気強く続ける必要があります。東京都新宿区にある「加藤レディスクリニック(klc)」は不妊治療専門のクリニックで、自然に近い状態で排卵を促す「自然周期療法」と呼ばれる独自の治療法を行っています。
klcでは薬の使用も最小限に減らして、心と体の負担を減らす治療を行っており、この概念に共感を持った治療中の方が多く受診されていると言われています。他にも不妊治療専門クリニックはありますので、自分に合ったクリニックを選ぶようにしましょう。
胎嚢の確認方法
経膣超音波
胎嚢は経膣超音波検査で確認します。経膣超音波検査とは、内診台に乗って検査用のゼリーを塗った棒状の超音波プローブと呼ばれる、専用の機器を膣内に挿入して検査することを言います。
妊娠初期は胎児の大きさがとても小さいため、主に経膣超音波検査で胎児の状態を確認すると言われています。経膣超音波検査を行うことで、早ければ妊娠4週目の中頃から胎嚢が確認できます。子宮内に胎嚢が確認できれば、正常妊娠となります。
経腹超音波
経腹超音波検査とは腹壁上でプローブを自由に広範囲に動かすことで、子宮の状態や胎児の形などを検査する方法になります。一般的に経腹超音波検査は妊娠中期から後期に経膣超音波検査から移行します。
しかし、産婦人科や産院・クリニックによっては、経膣超音波を置いていない場合があるため、そのような時は経腹超音波検査を行うと言われています。経腹超音波検査は、経膣超音波検査ほど正確に胎嚢が確認できない場合があるため、妊娠5週目頃には胎嚢が確認できない場合があります。
胎嚢確認後の流れ
胎芽確認
妊娠6週目頃に胎嚢の中に小さなリング状のものが確認でき、それを胎芽と呼び、成長を続けると胎児になります。胎芽の状態ではまだ人の形をしておりません。超音波検査で胎嚢が確認できれば、次回の受診日には胎芽の確認ができるでしょう。
胎嚢の確認ができなかった場合や最初に産婦人科を受診した時期が妊娠6週目頃だった場合には、胎嚢と一緒に胎芽を確認する場合があります。胎芽が確認できる時には、胎嚢の大きさは最初に胎嚢を確認した時と比べると胎嚢も大きくなっており、胎児の成長を実感することができます。
心拍確認
胎芽が確認できると同時に、胎児の心拍も一緒に確認することができます。子宮内に胎嚢及び胎芽が確認でき、心拍確認もできた場合には、流産の確率がぐんと下がります。実際に超音波検査を行っている時に、自身でもモニターで心拍が確認できるため、お腹の中の命の実感をすることができます。
まだ心拍が確認できない時は、胎嚢が子宮内に確認できても流産の可能性があるため、体調管理をしっかり行いましょう。流産の心配をして異常なほど不安に思うのも、心身ともに疲れてしまうため、普段通りの生活を行ったほうが良いでしょう。
胎児の心拍が確認できれば、ほとんどの自治体では母子手帳の発行を行います。母子手帳を持つことになると、自分が妊娠したことをより実感することができ、胎児の成長が楽しみになります。
胎嚢が確認できない理由
妊娠週数の数え方の誤り
妊娠した時には、一般的に最終月経初日を妊娠0週0日として妊娠週数を数えますが、最終月経の日が定かでなかったり、生理周期が不規則で排卵日が定かでない場合に、妊娠週数の数え方を誤ってしまう場合があります。
妊娠検査薬で陽性反応が出たが、産婦人科で胎嚢が確認できない場合には、妊娠週数の数え方が誤っている場合がありますので、自分の生理周期や最終月経日をしっかりと把握しておく必要があります。その時胎嚢が確認できなかったとしても、次の受診で確認することができることもあるので、不安に思わず過ごしましょう。
受診が早すぎた
妊娠検査薬は精度がとても高く、最終月経から4週間後には妊娠検査薬を使用して、妊娠が判明できるようになりました。しかし、胎嚢が確認できる時期は妊娠5週目頃と言われているように、その時期以前に産婦人科を受診しても、胎嚢の確認までには至らない場合があります。
妊娠を待ち望んだ方にとっては、妊娠検査薬で陽性を確認した時に、早く産婦人科を受診しようと思われるでしょうが、胎嚢が確認できないと意味がなく、診察代だけ損をする場合があるので、せめて妊娠5週目頃まで待ちましょう。
受診が早すぎて胎嚢が確認できない場合には、産婦人科医から週数を開けた次回の受診日を伝えられ、その時に胎嚢の確認を行いますので、不安に思わず落ち着いて待ちましょうね。
流産の可能性
妊娠5週目頃に産婦人科を受診し、経膣超音波検査で子宮内を確認した際に、子宮内に胎嚢が確認できない場合には、流産の可能性が考えられます。必ずしもすべてではないですが、この時期の流産は早期流産(妊娠12週未満)と言われており、妊婦全体の約15%が経験する妊娠最大の合併症と言われています。
早期流産の原因は、ほとんどが胎児側の問題によるもので、受精卵の染色体異常が原因と言われています。たまたま異常を持った精子、もしくは卵子が受精してしまったことで染色体異常が起きてしまうのです。
特に異常を持った卵子は、加齢とともに増えると言われているため、高年妊娠になればなるほど、流産する確率も高くなってしまいます。流産をしてしまうと、つい自分を責めたくなりますが、母体には何の問題もない場合が多いため、安心してくださいね。
早期流産の治療は流産手術を行いますが、完全流産(胎嚢が完全に子宮外に排出されること)の場合、まれに治療を行わず、経過観察することで月経が戻ってくることがあります。
しかし、子宮内に胎嚢が残ったまま放置してしまうと、出血や感染が生じ不妊の原因になるため、流産が確定したら早期流産の治療、流産手術を行います。流産手術は、まず子宮頚管の拡張を行い、静脈麻酔と呼ばれる全身麻酔を行います。そして、子宮内の胎嚢の除去を吸引法で行います。
子宮外妊娠の可能性
妊娠検査薬や産婦人科での尿検査で、妊娠していると判断できるのに、妊娠5週目頃に胎嚢が確認できない場合には、子宮外妊娠の可能性があります。
子宮外妊娠とは、子宮の外に妊娠した場合を言いますが、そのほとんどが卵管妊娠と言われています。卵管妊娠の場合、卵管に妊娠しているため、子宮内には胎嚢が確認できません。
経膣超音波検査で子宮外妊娠の疑いを持ちますが、そのまま子宮外妊娠を放っておくと、破裂してしまう場合があります。卵管妊娠の場合の破裂とは、卵管で成長した胎嚢が卵管を突き破ってしまい、出血を始めることを言い、結構な量の出血があります。
子宮外妊娠を判断するには、hcgホルモンの量が多くなっているか少なくなっているかによって、手術をするかしないかが決まります。子宮外妊娠と判断される方の18%程度は、勝手にお腹の中で流産し、不正出血を我慢すれば手術をせずに済みます。この時hcgホルモンの量が少なくなっている状態になります。
逆にhcgホルモンの量が多くなっている場合には、非常に危険な状態のため手術を急ぐ必要があります。卵管妊娠では腹腔鏡手術、もしくは開腹手術を行い、卵管を切除する方法(根治手術)や、妊娠部分を切り開き胎嚢などを出す方法(温存手術)で妊娠をやめる流れになります。
胎嚢確認後の体調変化について
出血
胎嚢を確認した後、人によっては微量の出血がある場合があります。この出血は「着床出血」と呼ばれる妊娠超初期症状の1つと言われており、通常は3日程度で出血が治まります。特に心配する必要もありませんが、出血の量が多かったり、心配で気になる場合は、産婦人科を受診したほうが良いでしょう。
腹痛
女性ホルモンの影響により、お腹の筋肉の筋が引っ張られるような痛みやシクシクした痛み、生理痛のような痛みなどの腹痛を訴える方がいます。これも妊娠超初期症状の1つで、人によっては痛みを強く感じたり、痛みを全く感じなかったりします。
この腹痛も特に心配する必要はありませんが、お腹の痛みが強くて動けなかったり、何か気になる痛みの場合には、早めに産婦人科を受診したほうが良いでしょう。
まとめ
胎嚢を確認する際の流れや確認時期、確認方法などについて紹介しました。胎嚢は妊娠検査薬で陽性反応が出た後、初めて形として確認できるものになるため、初めて妊娠をした人や妊娠を望まれる方にとっては、妊娠を実感できる1つになるのではないでしょうか。
胎嚢だけではまだ不安に思われる方も多いでしょうが、胎芽、心拍を確認できるのももう少しですので、楽しみに待っていてくださいね。その間は普段通り過ごして、不安な気持ちを払拭して過ごしてくださいね。