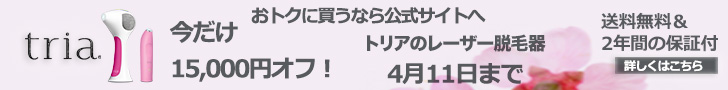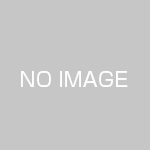[ひとりっこの介護コラム vol.7]父を看取ったあの日
長寿大国といわれる日本は、ご存知の通り高齢化社会まっしぐら。しかし、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間といわれている健康寿命と平均寿命のあいだには、男性で9年、女性で13年の開きがあります。
少子化の日本では、介護の問題が家族に重くのしかかります。いつか来る親の介護が心配、という人は少なくありません。そこで、毎週火曜日に人気介護ブロガーのひとりっこさんによる介護に関する連載をお届けします。
ご両親の介護を一人で背負われていたひとりっこさん。今はすでにお父様を見送られたそうです。介護の果てに送り出したときのお気持ちについて、書いていただきました。
父の願い
父は他人から理解されにくい人でした。父のイメージは「まじめ」「堅物」「几帳面」「偏屈」「口数が少ない」。務めていた会社では総務を担当し、定時になるとどこにも寄らず、いつも同じ時間の電車に乗り家に帰って来ていました。定年退職してからは、どこにも出かけることは無く、ずっと家に居ました。
庭いじりや家の補修等は、父の唯一の趣味みたいなものでした。ある時、私は父に「どうして老人会とかに入って、他の人と接しようとしないの?」と聞いてみました。「信じれば裏切られる。それなら他人と接触しなければいい。」この答えに、父の人生を、父の心の中を垣間見た気がしました。
「ずっと家に居たい」父のその願いを理解した私は、病院や施設ではなく、家で私が最期を看取ろうと決めたのでした。
父が亡くなったあの日
父は亡くなる数日前から、たびたび高熱を出していました。その度に病院に連れていったり、訪看さんに点滴をしてもらったりしていました。
父が亡くなったあの日、私はどうしても仕事を休むことができませんでした。訪看さんに来てもらうようにお願いし、母に私が帰るまで様子を見ていてほしいと頼み、仕事に出かけました。
仕事が終わり慌てて家に帰ると、父は自分の部屋の椅子に、ぐったりとした様子で腰かけていました。熱を測ると37.3度。手を触ると、熱があるはずなのに冷たい。再び訪看さんに訪問を依頼し、注射等の処置をしてもらいました。
訪看さんの指示通り、上体を起こす姿勢を保つようにしたため、いびき様呼吸も少し落ち着き、父は眠っていました。安心した私は、それまでの疲れからか、寝入ってしまったのです。
90歳の生涯を閉じる
少しだけ寝るつもりが、目覚めたのは午後10時半。父の様子を見に行くと、口の中が白い痰でいっぱいで苦しそうにしていました。口の中の痰を取り除き、背中から抱きかかえながら「口の中きれいになったよ。」「わかる?」と呼びかけても、反応がありません。目は開けているものの、視線は定まっていませんでした。
母は、同じ部屋の中で心配そうにずっと私たちを見ています。父の異変に気付いた私は、大声で主人を呼び、訪看さんに電話をしました。もう一度父に呼びかけると、少し大きくスゥっと息を吐き、目を閉じました。胸に手を当てても、鼓動は感じられません。脈をとっても、感じられません。
こうして父は、90歳の生涯を一人娘の腕の中で閉じました。
父親の深い愛情
自宅で老衰で亡くなる、これは父本人と私が望んだとおりの結末でした。
もし、父の命の限界が、私の身体と精神の限界より長かったら、家で最期を看取ることはできなかったでしょう。施設入所を決断していたと思います。当時の私はすでに、仕事と介護の両立に疲れ果てていました。
父が亡くなる朝に私が呟いた「もう、これ以上私の人生の邪魔をしないでくれる?」という言葉。寝ていた父に聞こえていたのかもしれません。これ以上娘に迷惑はかけられない、父親としての最大限の愛情表現としての逝き方だったと、私は思っています。
そんな父親の深い愛情により、私は見事に介護をやり遂げた孝行娘になることができました。
私が立派なわけではありません。父が守ってくれたおかげです。
葬儀の際、喪主の挨拶で「最愛の一人娘の腕の中で、静かに息を引き取った義父は、本当に幸せだったと思います。」と、主人が涙を浮かべて言ってくれました。介護は本当に辛い時があります。一人では絶対にできません。支えてくれる家族がいるおかげで、私は在宅介護を続けることができています。