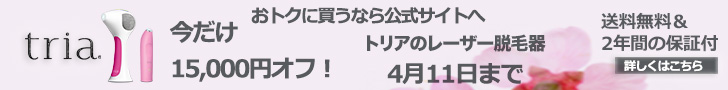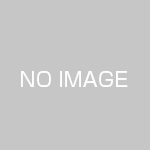アルブミンの働きで元気パワー促進!むくみや免疫力低下など不足で起きる5つの体の不調と食生活の乱れには要注意!
アルブミンとは?
「アルブミン」ってあまり聞いたことのない方もいらっしゃるかもしれませんが、実は気づかないうちに接しているかもしれません。例えば、血液検査の結果表には、「アルブミン」や「Alb」として検査値が表記されています。また、病気やケガの治療で痰黄色の液体「アルブミン製剤」が使用されることもあります。
アルブミンは体液に含まれるタンパク質で、血液中に約4割、組織(細胞の集合体)の中に約6割存在しています。アルブミンは、アミノ酸をもとに肝臓で合成されるタンパク質で、一日に約6-12g前後生成されて肝臓から血液中に入り、血液によって各組織の細胞に運ばれます。
標準的な成人の体内には、約250~350gのアルブミンが蓄えられていて、体の正常な機能を維持する上で、重要な働きをしています。この記事では、アルブミンの働きを分かりやすく説明し、アルブミンが不足する原因や不足したときに起こる体の不調について詳しく解説していきます。
アルブミンの働き
アルブミンは、栄養素と結合し運搬して、細胞を活性化する
ここで、アルブミンについてもう少し、詳しく説明させていただきます。血液に抗凝固剤を加えてから遠心分離器にかけると、血球と血漿に分かれます。この血漿には血漿タンパクという成分が含まれ、その血漿タンパクの約6割をアルブミンが占めています。このことからも、アルブミンは人体に不可欠な成分ということができます。
アルブミンの主な2つの働きのうちの1つは「結合と運搬」です。アルブミンには、いろいろな物質と相性よく結合する適応性があり、血液中に運ばれてきたカルシウムや亜鉛、脂肪酸、酵素、ホルモンなどの栄養素と結合して、これらの栄養素を各細胞に運ぶ働きをしていると言われています。
このアルブミンの「結合と運搬」作用により、体の各細胞の新陳代謝が高まると、細胞が活性化されます。ですから、健康を細胞レベルで考えると、アルブミンがしっかりと機能を果たしてくれることがとても重要です。
アルブミンには、体液を調整する働きがある
アルブミンの主な働きの二つ目は、「体液の調整」と言われています。 この体液の調整は、膠質浸透圧(こうしつしんとうあつ)と呼ばれる働きをアルブミンが支えていることで、血漿の循環量を保ち、浮腫みを予防することが可能になっているようです。
アルブミンが体液の浸透圧に果たす役割はとても大きいようです。アルブミンは、組織の水分を毛細血管の中に引き抜く働きをしていると言われていますから、アルブミンが不足すると組織内に水分が溜まり、組織が浮腫み、血圧が上昇することになります。アルブミンがきちんと働いてくれることで、細胞を満たしている組織液と血管中の血液の量を調度よいバランスに保っています。
また、健康な人の体の65%は、水分で満たされていると言われています。体内の水分の主な働きは、細胞の健康を維持することや体温を調整することですから、アルブミンが体内の水分調整をしてくれることで、むくみや乾燥といった極端な状態から守ってくれるようです。
またアルブミンは、ビリルビンなどの毒素とも結合し中和させる働きがあるので、血液透析に使用されることもあるようです。
アルブミンには老化を防ぐ抗酸化作用がある
アルブミンには、老化の原因と言われている酸化ストレスを抑制する働きがあると言われています。酸化ストレスというのは、呼吸や消化などにより体内で起きる必要な現象ですが、酸化反応と抗酸化反応のバランスが崩れ、体が酸化に傾くと、老化や動脈硬化、癌などの病気を促進する原因になってしまう状態のことです。
アルブミンは内因性抗酸化物質とも呼ばれ、その「酸化ストレス抑制効果」を期待する声は高いようです。アルブミンには、酸化型アルブミンと還元型アルブミンがあり、このうちの酸化型アルブミン自体が酸化することで、酸化ストレスを少なくすると言われています。
ある地域保健研究チームが行った調査では、血液中のアルブミン値が低いほど、認知機能が低いという結果がでたようです。これは、アルブミンと老化には深い関係があり、長寿の秘訣はアルブミンを不足させないことだという見方を支持するものとなっています。
アルブミンには、免疫力を維持する働きがある
アルブミンには、免疫力を維持する働きがあると言われています。アルブミンは、酵素と結合して各細胞に運搬するという仕事をしてくれますが、この酵素が免疫と深いかかわりがあります。酵素が不足すると、免疫細胞の代謝が悪くなり、免疫力の低下につながるようです。
また、癌にかかった場合、アルブミンが不足して免疫力が低下するので、免疫細胞を増やし免疫を上げるための治療を行う場合があるようです。ですから、体内に必要な量のアルブミンを保持し、不足させないことは、健康を維持する上で欠かせないと言えるでしょう。
アルブミンが低下すると?
アルブミンの基準値は、3.8-5.3g/dl
アルブミン(ALB) の量の測定は、血液検査で分かります。アルブミン値は栄養状態の指標とされることがあり、一般的な健康診断の検査項目に含まれている場合多いようです。アルブミンは血液中の血清の中に含まれています。ですから、採血した血液は検査室に運ばれ、凝固したところで遠心分離器で血清と血球成分に分け、その後、分析機械で血清中のアルブミン値を測定します。
★アルブミンの基準値は、3.8-5.3g/dlです。★
アルブミン値が3.8未満に低下すると、体内にアルブミンが不足しているということが考えられるでしょう。ドクターは、アルブミン値を病気の診断の材料としたり、アルブミンが不足している原因を明らかにするためにさらに検査をすすめることがあるかもしれません。
ただし、アルブミン値の測定には、様々な要因で誤差が出ることがあると言われています。現在は、すこしでも誤差を無くすためにBCP改良法という検査法を用いてアルブミン値の測定をすることが多いようですが、ドクターや検査機関によってさまざまな意見があるようです。
また、検査を受ける側の環境によっても検査値に誤差が出ることがあるようです。ですから、多くのドクターは、検査値の誤差も考慮に入れ、状況を総合的にみて、アルブミン値を診断の参考にするようです。以下に誤差が生じる要因のいくつかを列挙します。
・採血するときの姿勢・・・座位や立位で採血したほうが、寝た姿勢で採血するよりも、アルブミン値が高くなると言われています。座った姿勢では約5%、立った姿勢では約13%、アルブミン値が上がるようです。ですから、高齢者の栄養状態を推し量るためにアルブミン値を参考にする場合は、採血時の姿勢に留意したほうがいいようです。
・運動との関係・・・運動後に採血すると、アルブミン値は高くなると言われています。
・時間との関係・・・夕方に採血したほうが、早朝に採血するよりも、アルブミン値は高くなると言われています。
アルブミン値は、基準値を超えることはあまりない
体内にアルブミンが不足するとアルブミン値は低下しますが、アルブミンが過剰になって、アルブミンが高値を示すということは、ほとんどないようです。これは、私たちの体内に備わっているホメオスタシスという働きがあるためで、このホメオスタシスは体液成分や浸透圧、pH、体温などを一定の濃度や範囲に保ち、生命を維持してくれると言われています。
稀に起こるアルブミン値の上昇で考えられる原因は、「脱水症」です。アルブミンは体液という血管や組織に存在する液体の一部なので、体が脱水状態で血管や組織から水分が失われると、アルブミンの濃度が濃くなり、検査値が高く出てしまうようです。もちろんこれは、アルブミンの正確な検査値ではないので、脱水状態を改善してから、測定し直す必要があるでしょう。
栄養失調とアルブミンの不足には深い関係がある
体内にアルブミンが不足する原因は様々なので、「アルブミンの不足イコール低栄養」という判断は、必ずしも正しいとは言えないようです。なぜかというと、アルブミン値が低くても痩せが無く健康に過ごせている場合や、逆にアルブミン値が正常なのに痩せて実際の栄養状態が悪い、というケースがあるからのようです。これには、アルブミン値の測定が、代謝や炎症、感染症などの影響を受けることが関係しています。
これらのことからして、アルブミンの検査値だけを栄養状態の指標にするという考え方は、現在の医療現場では無いと言われています。しかし、アルブミン値が低い人が実際に低栄養状態であることも多いのは事実ですから、アルブミンの検査値を低栄養を見つけ出すためのスクリーニングとして用いたり、栄養管理の目安に用いる場合があるようです。
アルブミンの不足は、浮腫の原因となる
アルブミンが不足した状態のことを「低アルブミン血症」と言いますが、低アルブミン血症の状態では、腹水といって腹腔内に水が溜まったり、胸水といって胸膜腔内に水が溜まったりするようです。
これは、「アルブミンには、体液を調整する働きがある」の項目で前述しましたが、アルブミンは組織に溜まった水分を血管内に引き出す働きをしているので、アルブミンが不足すると膠質浸透圧が機能しなくなり、組織に水分が貯留し、結果として、体のいろいろな箇所に浮腫みが起こるようです。
「低アルブミン血症」による浮腫みが顕著に見られるのは、アフリカの飢餓状態にある子供たちのお腹が膨れていることです。たんぱく質の摂取が不足し、慢性的に栄養状態が悪いために、手足が浮腫んだり、腹水が溜まって下腹部が膨れているのを映像で見たことがあるかもしれません。
また、拒食症(神経性無食欲症)による低アルブミン血症によってもが浮腫むと言われています。このような低アルブミン血症による浮腫みに対しては、低カリウム血症の恐れがあるので利尿剤(排尿を促して浮腫みをとる)を使用するのは危険なようです。
アルブミンが低下すると、免疫力も低下する
アルブミンが体内に不足していると、免疫機能も低下してしまうと考えられています。これは、低アルブミン血症の原因が栄養不良である場合に、病原菌などの異物を攻撃してくれるリンパ球数が減少し、免疫機能が低下することによるようです。また、低栄養状態では、胃腸を細菌リスクから守っている粘膜のバリアも弱くなってしまうと言われています。
低アルブミン血症では、傷を治す力も低下すると言われています。これは、アルブミンの不足によって皮膚が浮腫むためのようです。また、アルブミンが少ないと、薬の分子と結合してを体の組織に運搬する働きも低下するので、抗生剤などの薬効が出にくくなると言われています。
実際のデーターでは、アルブミンが3.5g/dl以下の低栄養状態の人には免疫力に関係した次のような共通点があるようです。
・病気にかかりやすい
・合併症を起こしやすい
・傷がなかなか治らない
・入院が長期化しやすい
・死亡率が高い
低アルブミン血症では、筋力が低下する
低アルブミン血症の人は、筋力が低下するという特徴もあるようです。これも低栄養状態とのかかわりが深く、人は長期的に栄養摂取が不足すると、筋肉と脂肪が消耗してしまいます。筋肉量が減ると、日常の活動に負担を感じるようになり、すぐに疲れたりやる気が起きなくなります。こうした現象が、ADL(日常生活動作)の低下を招き、さらに筋力を低下させると言われています。
また、最近よく耳にするサルコペニア(加齢によって筋肉が減少していく)の原因と栄養不良に深いかかわりがあることが指摘されています。アルブミン値の低下は、低栄養状態の人を見つけ出すスクリーニングとしても用いられていますので、筋肉量の低下に低アルブミン血症が関わっている場合があると言えるようです。
アルブミンが不足すると、血圧が低下する
アルブミンには、組織の水分を血管内に引き込む働きがあり、そのことにより血液の循環量のバランスを摂っていると言われています。しかし、低アルブミン血症になると、水分が組織の細胞から血管に引き込まれないので、血液循環量が少なくなり、血圧が低くなると考えられます。
また、低栄養に関連した低アルブミン血症の状態が進み、呼吸するための筋肉や心臓の筋肉が低下することで、呼吸に障害が起こったり心臓の拍出量が低下すると言われています。これも低血圧の原因になるようです。
アルブミンが低下する原因は?
食生活の乱れはアルブミンを低下させる
アルブミンの低下を引き起こす原因として、「食生活の乱れ」を指摘する声は多いようです。食生活の乱れの要因として懸念されているのは、①甘いもののとり過ぎや②ダイエットです。
①甘いもののとり過ぎが、どうしてアルブミンの低下につながるのでしょうか?それは、スナック菓子やスイーツなどの糖分を過剰に摂取すると、それを代謝するために多量のビタミンやミネラルが使われるので、ビタミンやミネラルが不足してしまうことによるようです。
ビタミンやミネラルが不足すると、酵素の働きが悪くなると言われています。酵素はタンパク質を分解してアルブミンの原料であるアミノ酸に変える働きをしていますから、酵素が不足すると、アルブミンも不足してしまうということになるようです。
②ダイエットは、タンパク質の不足やビタミン、ミネラルなどの摂取不良を招きます。食事を抜いたり、ダイエット食ばかりを摂取していると、アミノ酸を作り出すためのタンパク質が不足し、アルブミンが不足する結果になってしまいます。
ですから、食生活を改善することで、低下したアルブミン値を上げることが可能だと言われています。また、中高年の方の場合は、動脈硬化や糖尿病を気にしすぎて食事制限をするあまり、たんぱく質の摂取が不足してしまわないように気を付ける必要があるでしょう。
肝臓・腎臓の機能低下がアルブミンを低下させる
1.アルブミンは肝臓で合成されるので、肝臓の機能が低下すると、必然的に低アルブミン血症を招くと言われています。ですから、血液検査で低アルブミン血症が見られる場合には、まず肝機能が低下していないかも同時にチェックする必要があるようです。肝機能が低下する原因には、肝炎や肝硬変などの病気が関係しているようです。
2.腎臓の機能が低下すると、アルブミンの原料となるタンパク質が尿中に排泄されることにより、低アルブミン血症になることがあるようです。特に、「ネフローゼ症候群」と言って、腎臓のろ過システムが障害されることで多量のタンパク質(アルブミンも含む)が排泄されると、アルブミン値が3.0g/dl以下になり、その結果浮腫みや腹水・胸水の貯留が起こるようです。
加齢によってアルブミン値が低下する
アルブミンは、加齢によってその量が減少すると言われています。なぜなら、加齢により肝臓の働きが低下するからです。アルブミン値は、1歳になるころには成人とほぼ同じ量になり、その後20-30代でピークになるようです。男女差はほとんどないと言われています。
しかし、30代を過ぎるとアルブミンは徐々に低下し、50代以降ではピーク時よりも0.3-0.4g/dL低下する場合があるようです。ですから、中高年者の中には、アルブミン値が低くてもBMI(肥満度)が正常か肥満となる場合があり、アルブミン値が低いからといって必ずしも栄養不足というわけではないようです。
アルブミンに関する検査
アルブミンが低下すると総蛋白も低下する
血液検査で「総蛋白」という項目を調べると、アルブミンの量とグロブリンの量を合わせた値が分かります。健康な場合、総蛋白の67%がアルブミンで、残りの33%がグロブリンです。総蛋白値が低下するというのは、アルブミンの量かグロブリンの量が少ないか、両方とも少ない場合が考えられます。
★総蛋白の基準値は、6.5-8.0mg/dl です★
総蛋白が低下した場合に考えられる病気は、肝障害やネフローゼ症候群、栄養不良、低タンパク血症などと言われています。また、総蛋白が高くなるのは、高たんぱく血症や慢性肝炎、多発性骨髄腫、脱水症などが考えられるようです。さらに「A/G比」や「アルブミン」の検査値を比較するとさらに原因が絞り込めてくる場合があるようです。
A/G比でアルブミンの低下が分かる
アルブミンに関係した検査で、「A/G比」という項目を採血で調べることがあります。このA/G比というのは、アルブミンとグロブリンの比率を示す値で、アルブミン値をグロブリンの値で割った数が表示されます。グロブリンというのは、アルブミンと並んで血漿タンパクを構成している成分で、主に免疫に関係した働きをしています。
★A/G比の基準値は、1.0-2.0g/dLです★
このA/G比の値が低い時に考えられることは、①アルブミンが低下していること、②グロブリンが増加していることです。また、グロブリンが増加する要因には、リンパ球が関わる悪性腫瘍や免疫系の病気などが疑われると言われています。
アルブミンが低下した場合に考えられる病気には、前述した肝障害やネフローゼ症候群、栄養失調のほかに、蛋白漏出性胃腸症、吸収不良症候群、甲状腺機能亢進症などが考えられるようです。ですから、アルブミン値だけを見るよりも、A/G比の値を参考にすることによって、病気の重症度を測ることができると言われています。
微量アルブミン尿検査では、腎臓の異常が分かる
腎臓の機能を調べるときに、「微量アルブミン尿」という項目を調べることがあります。腎機能障害の初期には、微量のアルブミンが漏れ出す場合が場合があり、この検査をすることで、腎障害を早期に発見できるというメリットがあるようです。
アルブミンを増やす食事
動物性たんぱく質を摂取してアルブミンを増やす
アルブミンは食事で増やすことが可能なのでしょうか?アルブミンの低下が栄養不良に関係している場合は、食事の改善でアルブミンの量を回復できると言われています。この場合ポイントとなるのは、「動物性たんぱく質の摂取」だそうです。
アルブミンは、たんぱく質を分解したアミノ酸を減量にして肝臓で作られるので、アミノ酸が多く含まれているタンパク質を食事でとると効果的です。「アミノ酸スコア」といって、食品の中に必須アミノ酸の種類がどれだけ含まれているかということを評価したスコアが満点の食品は、実は肉や魚、乳製品です。
ですから、肉や魚などのたんぱく質を含んだ食事をバランスよく食べることが、アルブミンの不足を予防し、改善する上で大切だと言えるでしょう。しかし、肝硬変が原因で低アルブミン血症になっている場合には、高たんぱくの食事を摂ると、血中アンモニア値を上昇させてしまい肝性脳症を引き起こすリスクがあると言われています。
肝機能が低下している場合には、食事療法について担当医とよく相談することが必要でしょう。
アルブミンに関する製薬
アルブミン製剤でアルブミンの低下を補う
アルブミン製剤というのは、人の血液からアルブミン成分だけを抽出した黄色い液体状の薬で、「血液製剤」に含まれます。アルブミン製剤は、血液中のアルブミンの不足を補う目的で、普通は点滴により血管から投与されます。
1.種類・・・高張アルブミン(高濃度)と等張アルブミン(低濃度)があり、目的によって使い分けるようです。
2.使用目的・・・高張アルブミン製剤は、低栄養や腹水・胸水、浮腫みの改善、肝機能が低下しアルブミンの産生が不足している場合などの目的で投与されます。等張アルブミンは、手術やケガで出血したり火傷などで血液中のアルブミンが失われた場合に、緊急にアルブミンを補充する目的で使用されることが多いようです。
3.副作用・・・アルブミン製剤を使用すると、呼吸器系や循環器系の重大な副作用が起こることがあると言われています。また、じんましんや発熱などが起きることもあるようです。
4.安全性・・・アルブミン製剤は人の血液をもとにつくられているので、使用することで細菌やウイルスによる感染症のリスクがゼロではないようです。より安全な薬を提供するために、血液製剤の安全対策は厚生省によってもすすめられています。
5.価格・・・アルブミン製剤は他の赤血球やグロブリンなど他の血液製剤に比べると、薬価はそれほど高くありません。25%アルブミン50ml入りのバイアルの場合、薬価は、6204円です。
アルブミン製剤の使用後にラシックスを投与すると徐水の効果があがる
医療機関で胸水や腹水、浮腫みを除去する目的で、高張アルブミン製剤を使用した後に、「ラシックス」という利尿剤を投与することがあります。これは、アルブミン製剤で組織から血管内に回収された水分を効率よく体外に排泄するためと言われています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?アルブミンは生命の維持に欠かせない体液の成分の1つです。水分の調整や栄養素の運搬などを担って私たちの体の中で働いてくれているタンパク質です。
アルブミンが不足すると、栄養障害や浮腫み、免疫低下や体力の低下など様々な体調不良が現れるかもしれません。また、アルブミンの不足には、加齢や肝臓や腎臓の病気のほかに食生活の乱れが関係していることも分かりました。ぜひ、甘いものの食べ過ぎや極端なダイエットには注意したいですね。
もしも、緊急な病気や怪我、胸水や腹水の除去などでアルブミン製剤の使用が必要になった場合には、副作用や安全性を事前に考慮することも大切です。よくドクターと相談してから、使用することが必要かもしれません。