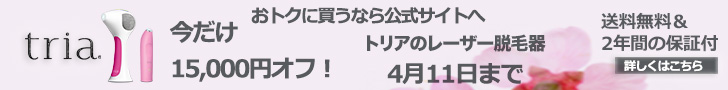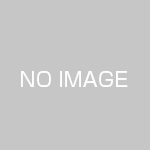いい子症候群がうつ病の原因に?!大人になった時の主な特徴とは?
“いい子症候群”になるとどのようなことが起こるの?
親の言うことをよく聞き、口答えをしない子が増えていますよね。親としては喜ばしいことなのですが、あまりにも自分の主張を表現してこないのであれば、”いい子症候群”である可能性が高いです。
いい子症候群の子供には、どのような特徴があるのでしょうか。また、このタイプの人は大人になるとうつ病になりやすいと聞きますが、実際どうなのでしょう。
いい子症候群について知ろう!特徴や原因教えます
まずは、いい子症候群について知ることから始めましょう。いい子症候群の子供や、その子供を持つ親の特徴、いい子でいる子供の心理などについて見ていきます。
いい子症候群には特徴がある
いい子症候群の子供に共通して見られるのは、常に親の顔色を伺っているという点です。大人になると当たり前に出来ることですが、幼い頃から顔色を伺う子供もいるのです。
さらに、その子は「何とかして親に好かれたい」「どうすれば、もっと愛してもらえるのだろうか」と、常に考えるようになります。期待にこたえようとして、いい子を演じてしまうのです。
子供はみんな親が大好きで、親の気を引こうとします。しかし、いい子症候群の子は度が過ぎてしまい、たくさん習い事をしたり、テストで100点を取るとめに休日もずっと勉強するなど、褒められることをしようとします。
あまりにもエスカレートしていると感じたら、親がストップをかけてあげる必要があるでしょう。子供が無意識に頑張り過ぎるのは危険です。
早いと小学校低学年から現れる
いい子症候群は、早い子だと小学校低学年から現れます。どうしたら親が喜ぶのか、だいたい理解できるようになるのが小学校低学年なのでしょう。
また、いい子症候群は長子に多く見られる傾向にあります。弟や妹ができた途端、母親の気を引こうとして頑張ってしまうのです。
多くの子は赤ちゃん返りをするなど「自分にも構って欲しい」という気持ちを素直に表現するのですが、いい子症候群の子供は素直になれず「頑張る」「我慢する」という表現方法をとってしまうのです。
いい子症候群の心理を紐解いてみよう
いい子症候群の子供は、自分がいい子でいることに疲れている可能性もあります。「もう、いい子でいることをやめたい」「いい子でいるのに疲れた」「我慢するのは嫌だ」と思っているのでしょう。
しかし、それを中々実行できないのが、いい子症候群の子供に見られる特徴です。いい子症候群は、子供が自分自身で解決することが難しいかもしれません。
親が気づいてあげて、子供に無理をさせないよう少しずつ促していく必要があります。まずは親がしっかりと子供に向き合うことが大事だという訳ですね。
いい子症候群になる原因は様々
いい子症候群になる子供を見てみると、なるべくしてなった理由があるように思います。原因の1つは、親の価値観を子供に押し付けているということでしょう。
第一子は特に親の期待が注がれやすく、親のこだわりや希望が強ければ強いほど「期待にこたえよう」と頑張ってしまいます。親の気にそぐわないことをして、そっけなくされたり叱られたりすることを恐れてしまうのです。
単に「褒めてもらいたい」という理由で、いい子でいようとする子供もいます。子供をいい子症候群にしないようにするためには、子供自身の自主性を尊重する育て方をするのがカギになってきますね。
子供をいい子にする親の特徴
「子供にはこうであって欲しい」という親の意志を押しつけがちな人が、子供をいい子症候群にしてしまう傾向にあります。そういった親は、決まって褒めるのが下手です。
さらに、子供に対する愛情表現も上手く出来ないからこそ、子供はそれを得ようとして頑張ってしまうのです。子供がいい子すぎると感じたら、まずは我が身を振り返ってみましょう。何か心当たりはありませんか?
いい子のまま大人になった人の5つの特徴とは?
いい子症候群を放置したままにしてしまうと、いずれ子供が成長した時に弊害が出る恐れがあります。大人になった時にどのような特徴があらわれるのか、ご紹介しましょう。
1.裏表の激しい性格になる
いい子症候群で子供時代を過ごした人は、その場の空気を読むことに長けています。人の心情を探り、嫌われないような行動をとるよう心がけるのです。
そのため、成長してもその癖が抜けず、裏表のある性格になってしまいがちです。職場や友人の前では親切な人のふりをしつつも、自分の子供にはきつくあたってしまうのです。
こうしたことにより、その人の子供が同じように良い子症候群になってしまいます。負のループが続いてしまうのが、なんとも悲しいですよね。
2.自分で動かず指示待ちになる
いい子症候群だった人は、自分の意見を言わないということに慣れてしまっています。そのため、大きくなっても自分の意志で動くということをしません。
常に誰かの指示を待ち、相手の指示通りに行動するようになってしまいます。自主性がなくなってしまうと社会生活において支障が出る恐れもあるので、なんとか防ぎたいところですね。
3.自己評価が低くなる
いい子でいようと頑張ってき続けたのは、親がなかなか自分を認めてくれなかったからです。そのため、自分のことを好きになれず、憎んでしまう場合も多いです。
決して劣っている訳ではないのに自己評価を低くしてしまい、ふさぎ込みがちになってしまいます。自意識が過剰なのも、それはそれで問題ですが、低すぎるのも悲しいものです。
子供が小さい頃、親が子供に「大好きだよ」「凄いね!」と、素直にほめてあげれば、きっと防げます。なんとか自分のことを好きになってもらいたいものですね。
4.個性の無い人間になる
あれをしたい、これをしたいという意志がなくなってしまうため、自然と個性がなくなってしまうという特徴もあります。子供時代にワガママを言うのは、意外と重要なことなのです。
空気を読む、周りに合わせるということを再優先に考えた結果、人についていく人間になってしまいます。その子にあったものを見つけて、しっかり褒めて伸ばしてあげることもまた親の役割なのかもしれませんね。
5.新型うつ病になりやすい
いい子症候群は、新型うつ病との関係性もあるのではないかという指摘もあります。親子関係で受けた影響が、社会に出てからも続いてしまい病気にまで発展してしまうのは辛いです。
いい子できたからこそ、怒られることに慣れていない人がいたとしましょう。その人が職場で上司にミスを指摘されただけで大きなショックを受け、そこから立ち直れなくなってしまうこともあります。
塞ぎこんでしまい、結局は自分の部屋から一歩も出られなくなったと言います。見かねた家族が病院へ連れて行ったところ、うつ病だと診断されたようです。こうならないためにも、幼少期からのいい子症候群には要注意です。
いい子がうつ病になりやすい4つの理由
どうして、いい子症候群の人はうつ病になりやすいのでしょうか。考えられる4つの理由についてご紹介します。
1.失敗に慣れていない
幼い頃から親や周囲の顔色をうかがってきたため、はたから見れば「いい子」だと思われていたはずです。そのため、周囲をガッカリさせるような失敗を極力避けてきました。
失敗するということに慣れていないで困るのは、いざ独り立ちした時です。就職や転職など、人生の節目において思い通りにいかないことは誰しもあります。
そういった時、失敗を修復する方法を知らないと「もう何もかも駄目だ」と、絶望の淵に立たされてしまうのです。そのまま塞ぎこんでしまい、立ち直ることが出来なくなってしまいます。
2.自分の能力が発揮できない
いい子症候群だった人は常に自分の思いよりも親や周囲の意見を気にしてきたので、自主的に動くことが出来ません。そのため、大人になっても自分から動くことが出来ないのです。
思うように実力を発揮できず、そのため自分を嫌いになってしまいがちです。何か得意分野があれば、それが親の望みと違ったとしても応援してあげるべきでしょう。そうして本人の意志を尊重してあげることが、子供の明るい将来へと繋がります。
3.対人関係が苦手
いい子症候群で過ごしてきた人は、自分が我慢をすることでその場を取り持ってきたのです。そのため、対人関係が得意ではないという人が多いです。
素直な気持ちで人と向き合えず、相手の顔色をうかがってしまいます。対人関係が苦手だと、物事をうまく処理できなくなることが多いのでしょう。
対人関係のストレスから、精神的な病気を発症してしまう場合が多いのです。うつ病の人の多くは対人関係が得意ではないと思います。その根源は、実は幼少期にあったのですね。
4.ストレス解消がうまく出来ない
人生の中で、ストレスを感じる瞬間は数えきれないほどあるかと思います。その1つ1つを重く受け止めていては、身も心も持ちません。
しかし、いい子症候群だった人は、そうしたストレスへの耐性がありません。常にいい子だったので、ストレスを感じずに育ってしまったからでしょう。
ストレス解消が上手くいかず、深く悩んでしまうようになります。大人になればなるほどストレスは増え、負のループにハマってしまうという訳です。しまいには、あるストレスが引き金となり、うつ病を発症してしまうのです。
いい子症候群を予防・改善する方法を紹介します
いい子症候群の傾向にある子供に対して、親はどう接していけば良いのでしょうか。予防・改善に効果的な方法を2つご紹介します。
1.親の理想を押し付けない
子供の意志を尊重するためには、まず親の理想を押し付けないよう気をつけるのが重要です。可愛い自分の子供だからこそ「こうあって欲しい」と願うのは分かりますが、それを押し付けるのはやめましょう。
まずは、子供の自主性を尊重してあげてください。選択肢が目の前にあるときには親が選ぶのではなく、子供本人に「どれがいい?」「何をする?」と尋ねてあげると良いでしょう。
2.自分で頑張ったことを褒める
子供は、親がなかなか褒めてくれないと、必要以上に頑張ってしまいます。それを予防するには、とにかく褒めてあげることです。
特に、子供が自主的に頑張ったことに関しては、大いに褒めてあげましょう。子供はそれを自信にして、新たなことへ挑戦しようとします。子供の自主性を伸ばすには、褒めることが大事ですよ。
いい子症候群には早めに対処しよう!
子供は親に好かれようとして、一生懸命頑張ってしまうものです。あまり無理をさせないよう、親が気遣ってあげることが何より重要です。
今までより分かりやすく褒めたり、分かりやすく愛情表現をしてみてください。きっと子供には伝わりますし、素直な気持ちをぶつけてくれるようになるでしょう!