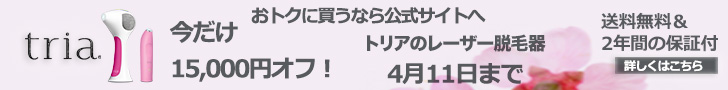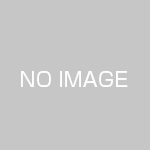【多臓器不全の原因・治療】敗血症や老衰など理由は様々?身体を守る予防法も解説します!
多臓器不全とは?
多臓器不全という言葉を誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
多臓器不全は体の多くの臓器が不全になるという大まかなことは名前から判断することができるかもしれませんが、実際に多臓器不全について知っている人は少ないと思います。
多臓器不全とは一体どんな病気なのでしょうか。
多臓器不全とは多臓器不全症候群のこと!
多臓器不全は「多臓器不全症候群」の略式の言い方で、私たちが生きていく上で必要な腎臓、肺、肝臓、心臓、血管系、消化器、神経系の中の2つ以上が同時か短時間に相次いで機能不全になった状態のことです。
敗血症などの感染症や重度のやけどなど原因は様々で、多臓器不全に陥ってしまうと治療することはほとんどできないと言われています。
そのため、多臓器不全になる前にできるだけ早い処置や予防をする必要があります。
多臓器不全の症状とは?
多臓器不全を早期発見するためにはどんな症状が現れるのか知っておくことが大切です。
ここでは多臓器不全の症状をいくつか紹介したいと思います。
1.肺の機能不全
肺の機能は多臓器不全の中でも一番早く症状が現れる場所だと言われています。
多くの場合、肺水腫を伴った低酸素血症になっているそうです。
・肺水種とは…
肺は酸素と二酸化炭素を交換する大切な部分です。そのためには肺胞と呼ばれる小さな袋状の部分を使うのですが、肺胞の周りには毛細血管と呼ばれる網目状の血管が取り巻いており空気と血管の間で酸素と二酸化炭素を交換します。
肺水腫とは、毛細血管から血液の成分が肺胞内に滲み出た状態で、肺胞の中に液体が溜まると酸素がうまく取り込めなくなり最悪の場合、呼吸不全になります。
▼関連記事
2.肝臓機能の障害
次に症状が現れやすいのが肝機能です。
結成酸素が上昇することで肝不全になったり、重度になると肝性脳症にまでなることも。
・肝性脳症とは…
肝機能が低下することにより中枢性の症状を発症する状態のことです。
肝硬変や肝炎などが悪化することにより解毒されるはずの有害物質のアンモニア類が体に溜まることが原因の1つと考えられています。
症状により肝性脳症は5段階に分けられます。
昏睡1:興奮や抑うつ
昏睡2:軽い傾眠状態、異常行動、意識障害
昏睡3:嗜眠状態、極度の怯え、興奮状態
昏睡4:意識を失い昏睡状態になっても痛みや刺激に反応がある。
昏睡5:意識を失い昏睡状態になり痛みや刺激に対する反応もなくなる。
3.消化器系の障害
消化器系の障害として、腸閉塞や消化管からの出血が見られることがあります。
・腸閉塞とは…
腸閉塞とは別名「イレウス」とも呼ばれており、食べ物、ガス、便などが適切に排泄されず大腸や小腸に溜まってしまうことです。
大腸や小腸に食べ物などが溜まると腸が広がり滞っている食べ物などが逆流して嘔吐や吐気の原因になったり、進行すると腸管の壊死や穿孔の原因となる動脈血流障害になり生命の危険も。
▼関連記事
4.血液系の異常
血液系の異常として、貧血になったり心循環障害による不整脈や低血圧といった症状が多臓器不全の後半に現れることがあります。
・不整脈とは…
不整脈とは脈の打ち方が不規則な状態のことです。
脈拍1分間に50以下の場合を除脈、100以上の場合を頻脈といいます。
人は運動をした後や興奮状態、熱がある時など脈が速くなることがありますが、これは生理的な頻脈で誰にでも起こる不整脈です。
また、加齢とともに起こる不整脈に「期外収縮」があります。
30歳を超えるとほぼ全員に見られる症状で、一般的に脈拍1分間に40以下になるとめまいなどの症状が出やすくなると言われています。
一方、突然脈拍が120以上になる頻脈の場合、病気が原因になっている可能性があります。
頻脈は動悸や息切れ、胸が痛むといった症状のほかに失神してしまうこともあります。
▼関連記事
5.体全体に起こる症状
多臓器の部分によって症状は異なりますが、全体を通して主に神経障害や意識レベルの低下が見られると言われています。これらは中枢神経障害になるため、病期に関係なく出現するそうです。
・中枢神経障害とは…
中枢神経障害の多くは、脳に原因があると考えられているため精神疾患、神経障害、心理的障害、適応障害などがあります。
しかし、中枢神経障害の根本的な治療方法は未だ解明されていないため薬物治療なども難しいとされています。
中枢神経障害には精神科と神経科の2種類があります。
「それぞれの代表的な病気」
精神科
・不安障害(パニック障害、対人恐怖症など)
・うつ病
・統合失調症
・小児精神医学(多動症、注意欠陥、ダウン症、小児うつ病など)
神経科
・アルツハイマー
・パーキンソン病
・ハンチントン病
・てんかん
・片頭痛
・睡眠障害など
多臓器不全の原因とは?
1.敗血症などの重症感染症
重度の感染症になると私たちの体は細菌が血液中に入り込み全身に回る「菌血症」なります。
また、血液中に細菌が入っていかなくても細菌が出す毒素などにインターフェロンやインターロイキン、腫瘍壊死因子が反応します。
本来ならインターフェロンやインターロイキンは炎症などに対する生体防御反応ですが、重い感染症になるとサイトカインやホルモンと言った各種化学伝達物質が過剰に作られます。
すると、血管内皮細胞が強力に活性化してしまい、制御不可能になり各臓器に悪影響をあたえてしまい結果多臓器不全の引き金になると言われています。
2.様々な原因で起こる重度のショックや低血圧
例えば、重度の怪我やショックを受けると血液が足らなくなり低血圧になります。
すると、体の中の臓器は血液不足や酸素不足になり組織内低酸素血症になります。
組織内低酸素血症になると細胞に大切な栄養や酸素が行かなくなり生命維持に大切な臓器の細胞が壊れて、結果機能を維持することができなくなります。
そして、最終的に臓器不全になり多臓器不全の予備軍になっていくと言われています。
▼関連記事
3.多臓器不全になりやすい様々な病気
多臓器不全は様々な要因によってなりうる病気です。
基本的な原因は上記で説明しましたが、その他にも多臓器不全になる可能性のある病気を紹介しましょう。
・重症感染症
・外傷
・大手術
・ショック
・膵炎
・大量出血
・播種性血管内凝固症候群(DIC)
・心不全
・低血圧
・低酸素血症
・悪性腫瘍
多臓器不全の治療・対策法って?
1.原因となっている病気などの改善
まず第一に行うのが臓器不全になっている原因を取り除くことです。
例えば出血が多ければ止血して輸血をしたり、感染症になっているのであれば感染症の治療します。
機能不全になっている根本の原因を改善しなければ、その部分が引き金になり新たな臓器が機能不全にならないようにしなければいけません。
2.多臓器不全になっている臓器に対する治療
多臓器不全は体のどの機能が悪いのかによって治療や対策に違いがあります。
呼吸器系が機能していないのであれば人工呼吸をしたり肺が機能していないのであれば人工肺を使います。
それぞれの臓器の症状に合わせた治療方法を見てみましょう。
・腎不全の治療
透析
・肝不全の治療
血漿交換
・心不全の治療
循環作動薬、補助循環装置
その他にも、高血糖や低栄養にならないために栄養を考えた食事をとったり場合によっては血液の浄化や薬物療法を用いることもあります。
ただし機能不全になっている臓器が1つだった場合、その臓器の治療に専念しすぎると他の臓器に悪影響を与えることがあります。
そのため、体に違和感を感じたら必ず一度病院を受診するといいでしょう。
多臓器不全の予防法とは?
多臓器不全は一度発症してしまうと生存率がとても低いため、日頃から多臓器不全にならないように予防することがとても大切になってきます。
そのためには、多臓器不全の主な原因になる感染症や低血圧などの対策をすることが一番です。
1.低血圧を予防する
低血圧を予防するにはどうしたらいいのでしょうか。
低血圧は不規則な生活(食事の摂取が不規則、寝不足)によって引き起こされることがあります。
食事をとらなければ私たちの脳はブドウ糖が不足してしまい正常に働かなくなることがあります。
特に、女性はダイエットで食事の摂取を制限してしまうことがありますが1日3食はきちんと食べるようにしましょう。
また、食事療法として塩分やたんぱく質を積極的に摂取することが予防になると言われています。
塩分には血管を圧迫する性質があり血圧をあげる働きをしてくれます。
たんぱく質も不足しがちな成分の1つで、チーズ類には血圧をコントロールする成分も含まれているので低血圧予防にオススメの食材とされています。
低血圧はアルコールの摂取量でも変わってきます。
アルコールは血管を広げる作用があり、血圧が低くなります。
もとから血圧が低めの人がアルコールを多量に摂取すると、場合によっては起立性低血圧になることもあるので注意しましょう。
重症感染症に気をつける
重症感染症は一般的な感染症よりも症状が重い感染症のことです。
風邪やインフルエンザといった病気も感染症ですが、一般的な感染症とは違い抗生物質を3日間投与しても症状が改善されないのが特徴といわれています。
中でも、多臓器不全の原因となるのが敗血症や肺炎などの重度の感染症です。
風邪の進行型ともいえる肺炎の予防はマスクの着用や手洗いうがい、肺炎球菌のワクチン接種で予防することができるので、免疫力が低い高齢の人や子供は積極的にワクチン接種が推進されています。
手術後に起きる感染症などは予防することができませんが、感染症自体を重くしないためにも体の免疫力アップをすることが重症感染症の予防になります。
多臓器不全は何科?
多臓器不全は体のどの臓器が悪くなったのかによって受診する診療科目が違います。
基本的に体に一番に現れた症状に適した科目を受診するといいでしょう。
例えば、多臓器不全の原因の1つである敗血症でも何が理由で敗血症になったかによって受診する科目に違いがあります。
敗血症でも手術が原因でなる場合もあれば、糖尿病や悪性腫瘍といった疾患が理由で敗血症になる可能性もあります。
また、臓器の細胞に必要な栄養や酸素が行き渡らなくなる低血圧の受診は循環器内科が一般的です。
その他にも、大量出血が原因で多臓器不全になっているのであれば外科による手術が必要になりますし、未熟児で生まれたことで臓器不全が起こっている場合は小児科の受診が必要になってきます。
多臓器不全の原因になっている部分を治療しなければ根本的な改善になりませんので、体の悪い臓器に合わせて治療する診療科目を選ぶようにしましょ。
まとめ
多臓器不全は「そういう病気だ」と思われがちですが、実際は体の大切な臓器が同時に2つ以上機能が正常でなくなるか相次いで機能に不調が現れた多臓器不全症候群のことだとわかりました。
そのため、多臓器不全になる前に体のどの部分で不調が起こっているのかを知ることが多臓器不全を事前に防ぐ方法になります。
健康診断はもちろん、ただの風邪でも「そのうち治るだろう」と放置しておくと肺炎などの重症感染症に発展するかもしれません。
多臓器不全になってしまうと生存率0~15パーセントと言われており、決して高い数字ではありません。
どれだけ早い段階で多臓器不全に気づくかどうかが大切になってきます。
重度の感染症など必然的に病院を受診したほうがいい病気もありますが、低血圧だけで病院を受診する人は少ないと思います。
小さな体の不調でもそのままにしておくと大きな病気に発展する可能性もありますので、自分の体に対して少しでも不安があれば一度病院を訪れてみましょう。