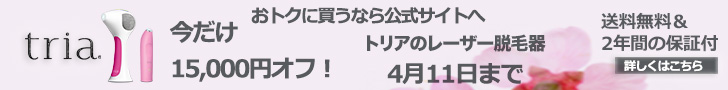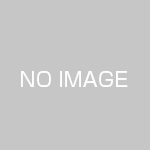糖尿病は予防できるの?自覚症状が無くても油断しないで!効果的な7つの食品や4つの運動などの秘訣をお教えします!
合併症が怖い!糖尿病を予防するには?
糖尿病にもしかかってしまったら、様々な食事の制限を守らなければならなかったり、薬を毎日欠かすことができなくなったりととても不自由な生活が待っています。
糖尿病は初めは自覚症状が少ないので気がつきにくいといわれています。それが故に放置しやすく、もし糖尿病と診断されても生活習慣をなかなか変えることができず症状を悪化させやすいのが問題です。
糖尿病を発症しないで済むならばそれに越したことはないのです。ここでは糖尿病に関する基礎知識から、特に予防法に着目して解説していきたいと思います。将来、糖尿病になりたくないならば読まないと損ですよ。
糖尿病とは
慢性的に高血糖になる病気
糖尿病という名前をご存知の方は多いかと思いますが、実際どのような病気かはご自分のことにならないと理解できていない場合が多いかと思います。糖尿病は慢性的に高血糖になる病気です。高血糖になると何が問題なのでしょうか。
私たちは食事から糖分や炭水化物などの栄養分を摂取して、消化吸収してブドウ糖という小さな糖にまで分解して利用しています。ブドウ糖は筋肉や脳などでエネルギー源として使われます。
体の中で血糖値は食事をすると上昇しますが、正常な体であればインスリンなどのホルモンの働きによってコントロールされて適正な範囲に保たれています。
しかし、インスリンが出にくくなったり、効き目が悪くなったりすると血糖のコントロールがうまく出来なくなり血糖値が異常に上昇したり、下がりにくくなったり、上下する変動が大きくなることがあります。
国民の5人に1人は予備軍
糖尿病は日本人でも食事の欧米化にともなって増えてきています。最近では子供でも糖尿病と診断される子も増えているそうなのです。
最近の調査によると、予備軍と思われる人も含めると2,050万人にも及び、国民の5人に1人が糖尿病の可能性があるといわれているのです。糖尿病はとても身近な病気で、あなたもかかる可能性が十分にありうる病気といえるため、予防して糖尿病にならないようにしなければいけません。
合併症が問題となる
糖尿病は自覚症状が初めは少ないので、なかなか気がつきにくいといわれています。また、高血糖の時ですらも自覚症状に乏しく、自分の血糖の状態は感覚としてわかりにくいようです。そのため糖尿病の患者さんは自分が病気であることを忘れがちになってしまい、症状を悪化させてしまうことも多いのです。
しかし、糖尿病が怖いのはその合併症が問題だからです。合併症としては毛細血管と細小血管に障害が起こりやすく、「細小血管障害」といいます。具体的には、腎症、網膜症、神経症があります。たとえば網膜症が悪化すれば失明するリスクもあり、神経症が原因で足が壊死してしまうこともあるのです。
また、大きな血管に問題が起こる場合もあり、糖尿病の合併症として動脈硬化も切実な問題といわれています。他にも狭心症や、心筋梗塞にもなりやすくなるため、命が危険になる場合もあるのです。
2つのタイプがある
糖尿病には大きく分けて1型、2型の2つのタイプがあります。1型糖尿病は日本人にはあまり多くないといわれていますが、ウイルスなどによる膵β細胞の障害が原因で自分の膵臓細胞を攻撃して破壊してしまいます。結果として、インスリンがほとんど分泌できなくなってしまい、インスリンを自己注射しないと生きられなくなるのです。
成人になってから発症する糖尿病のうちほとんどが2型糖尿病といわれています。40歳以上で発症することが多いとされていて、遺伝的な要因も大きいのですが、インスリンの効き方が低下するのが原因になります。食べ過ぎや生活の乱れから発症することが多い為、生活習慣病とも呼ばれています。
糖尿病の自覚症状チェック
尿の量が多くなる
糖尿病にはほとんど自覚症状が初めはないといわれています。ここで挙げる自覚症状が見られたら、糖尿病があるていど進行してしまっている可能性があるため注意が必要です。
まず自覚症状としては尿の量が多くなりやすいといわれています。これは、余分な糖を外にだすために尿中の糖も増える傾向があるためです。糖は尿に出るときに、同時に水分も一緒に出すために、尿の量が多くなってきます。
のどが渇いて水分をたくさん摂る
汗をかいたり特にしていないのに、のどが渇いて水をたくさん飲みたくなる多飲とも呼ばれる症状が出ることがあります。これは糖を外に外に出すため尿の量がふえて脱水状態となり、のどが渇いて水分をたくさん飲みたくなるために起こる現象といわれています。
体重が減る
糖尿病の患者さんは太っているイメージが強いかもしれませんが、瘦せ型の人でも糖尿病になる場合があります。運動をしたり、食事の量も変わっていないのに体重が急激に落ちたというときは危険です。これは、糖が尿に出ていくことで、代わりにたん白質や脂肪を利用してエネルギー源とすることが原因です。
疲れやすくなる
自覚症状として疲れやすくなったりダルく感じるということもあります。これは糖尿病の方の場合、インスリンの効き目が悪くなっているので、細胞や組織などにブドウ糖を取り込む力が落ちていることが原因です。
インスリンが正常に聞いていれば体内でブドウ糖を効率よく筋肉などに取り込んで使うことができるのですが、糖尿病になるとエネルギー効率が悪くなるため倦怠感や疲労感などを感じるようになります。
糖尿病の原因
遺伝
親や肉親が糖尿病だと、糖尿病の家族歴がない人と比較して 糖尿病になりやすいといわれています。しかし、遺伝するのは糖尿病そのものではなくて、糖尿病になりやすい体質だといわれています。
この体質を持っていると、食べ過ぎ、運動不足、肥満、加齢、ストレス、など様々な環境的な要因が加わってはじめて糖尿病が発症すると考えらているのです。つまり親が糖尿病だからといって絶対に発症するとは限らないのですが、不摂生をしてしまうと糖尿病になる可能性が高まってしまいます。
肥満
肥満も糖尿病の大きな原因になります。日本人も最近は肥満の方が増えてきてしまっているのが問題になっています。肥満と糖尿病は大いに関係があるため肥満にならない努力が必要です。
肥満になると体内で糖をエネルギーとして消費したり、蓄えたりする役割を果たすインスリンの必要量が増増加して、インスリンを産生する膵臓が、「肥満」という異常な状態に対応しようとします。肥満が続くと、膵臓はどんどんインスリンを分泌しようと大きく肥大して、いずれ何からの障害を起こしてしまうと考えられています。
ストレス
ストレスがあると血糖値を上げるホルモンが分泌されると共に、インスリン抵抗性が高まりインスリンの効きが悪くなり血糖値が上がりやすくなるといわれています。
また、ストレスがあると過食をしやすくなり、肥満につながることも原因と考えられます。ストレスは様々な病気の原因になりますが、糖尿病にも大いに関係しているのです。
加齢
小児で発症する糖尿病の場合は1型糖尿病が多いのですが、大人になってから発症する糖尿病は2型糖尿病がほとんどです。加齢は糖尿病のリスク因子になります。データからも糖尿病にかかりやすいのは中高年以降だといわれています。
これは加齢に伴い、インスリン分泌が低下することが原因です。また、筋力が低下して脂肪の割合が増加することにより、インスリンに対する反応性が低下してしまいます。他にもあまり動かなくなることで消費エネルギーが減って、肥満傾向になりやすいことも関係しているようです。
食べすぎ
糖尿病は食事が原因のことが多く、2型糖尿病の95%が食事と運動が原因ともいわれているそうです。食べ過ぎは糖尿病の大きな原因となり、食事の偏りや、不規則な時間に食べることも原因となるといわれています。
特に食べ物で気をつけなければいけないのが「糖質」です。以前は、糖尿病には糖質以外にも脂質やたんぱく質も摂取を控えるべきといわれていましたが、糖質制限をすることが大切だと分かってきています。内容に気をつけつつ、常に腹八分目を意識して食べることが病気の予防につながります。
運動不足
糖尿病は運動不足も原因です。食べたいだけ食べて、運動もせずにゴロゴロとしていると糖尿病になりやすくなってしまいます。これは糖分は筋肉に取り込まれてエネルギー源として利用されることで減少していくので、運動不足だとエネルギーとしての消費が低下してしまうことが原因です。
また運動不足になると太りやすくなって肥満になってしまう確率が上がります。運動不足にならないように、日頃から継続して運動を取り入れていくことが大切です。
糖尿病の予防法
規則正しい生活
規則正しい生活を送ることは糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防には基本です。食事の時間が不規則だったり、睡眠時間が不十分だったり夜更かしをしたりと、不規則な生活を送っているとホルモンなどの働きを悪くしてしまいます。
また食事の時間がバラバラだったり、夜遅く食事をしてすぐ寝るような生活をしていると糖尿病になりやすくなってしまうと考えられます。規則正しく、いつもだいたい同じ時間に食事をとり、睡眠時間を十分に確保してリズムよい生活を送るようにしましょう。
適度な運動
糖尿病の予防には適度な運動が効果的だといわれています。運動すると肥満予防にもつながり、日々エネルギー代謝の良い生活を送ることができます。
適度な運動というと、どんな運動を、どれ位が良いのか気になるところですね。運動の内容としては有酸素運動がおすすめで、時間がとれるときは、1回10~30分間程度の有酸素運動を週3~5日以上行うとよいといわれています。たとえばウォーキングなどがおすすめです。
まとまった時間が取れないならば、家の中でなるべく家事をして働くようにしたり、日常的にエスカレーターなどを使わずにエレベーターに乗るようにするなど、生活の中で運動するようにするだけでも違いが生まれます。
バランスの良い食事
バランスよく食事を食べることは糖尿病の予防につながります。糖尿病を発症してしまった場合には糖質制限食などが推奨されますが、まだ糖尿病になっていない段階から糖質を制限しすぎるのはよくありません。
野菜や肉、魚などのタンパク質、穀類、海藻類、お米のなどの主食をバランスよく食べて、偏りの少ない食事を心がけるようにしましょう。無理なダイエットや過食などの極端な食生活を続けていると健康を害することになってしまいます。
糖尿病予防教室
それぞれの自治体で糖尿病予防教室というのが実施されているのをご存知でしょうか?糖尿病の方、または糖尿病に関心のある方を対象として行われていて、体組成測定、糖尿病についての概要、調理実習、運動実技などの糖尿病予防に役立つ知識を身につけることができるそうです。それぞれの区役所、市役所などに問い合わせてみると良いでしょう。
糖尿病の運動による予防
どんな運動でもOK
運動をすると血糖値が下がります。どんな運動でも何かしら体を動かすことは効果があります。特に有酸素運動が糖尿病予防には大切といわれていますが、最近の研究では筋トレも有効だということが分かってきているようです。
運動が苦手な方は、場所や時間を選ばないで行うことができる運動がおすすめです。どんな運動でも良いので、とにかく日々の活動量を上げて毎日活発に動いてエネルギー消費をうながしましょう。
食後が効果的
運動をするタイミングはいつがベストなのでしょうか。「食事の1時間前」、「食後1時間後」、「食後3時間後」での運動による血糖値の減少を調べた調査によると、どのタイミングでも運動により血糖値は下がりました。特に食後1時間の運動ではちょうど血糖値が上がるタイミングと運動の時間が重なるので、血糖値の上昇を抑えられたということです。
運動するならば食後が効果的ですが、食直後は胃が痛くなったり消化の邪魔になるので少し食休みをしてから運動を開始すると良いでしょう。食後は難しくてもこだわらずに、自分の生活リズムで運動をしやすい時をみつけてください。
ウォーキングが効果的
運動として効果的といわれているのが特にウォーキングです。頑張って走ろうとしなくても良いとなると安心しませんか?ウォーキングであれば普通は誰にでもできる運動です。
足には筋肉がたくさんあり、足を使うことは運動の中でもエネルギー消費が高くなるといわれています。1分間に80mを目安に、会話ができる程度で少し息が上がる程度のスピードで始めましょう。最低でも30分以上は続けたほうが効果的です。毎日行うのがより望ましいですが、週に3日以上は行うようにすると良いでしょう。
毎日楽しく続けられるもの
運動があまり好きじゃないというかたは、運動しなさいと言われるだけで急に逃げたくなってしまうかもしれません。しかし運動は辛いことばかりではなく、適度な運動であれば終わった後に心地よい爽快感が得られるものです。
激しい筋トレや、長時間のジョギングなど難易度の高い運動をしようとしなくて構いません。ストレッチやヨガなどはリラックス効果もあり、ストレスによる食べ過ぎを防ぐこともできます。毎日楽しく続けられる運動をおこないましょう。
糖尿病の食事による予防
栄養バランス良く食べる
栄養バランスよく食べることが糖尿病の予防には基本です。糖質や脂質などに偏った食事や、間食が多かったり、毎日食べる量が一定でなく不規則だったりすると、体にとって負担になってしまいます。
食卓に並ぶ献立として、毎食に主菜・たんぱく質の多いおかず、副菜・野菜料理があるのが望ましく、小鉢がいくつか並ぶようなイメージで食事のバランスを考えましょう。
外食が多い人は、カツ丼、牛丼やカレーのような単品メニューを選ばずに、なるべく魚などが入った定食メニューなどを選ぶとバランスがよくなります。また、自分でお弁当を持参して食べるのが良いでしょう。
1日の摂取カロリーを守る
1日の摂取カロリーは体型によって違いがありますが、一般的な成人の一日の摂取カロリーが1800~2200 キロカロリー前後といわれています。カロリーだけではなく、食べ物の内容を気にすることが大切ですがカロリー計算は肥満を防止するために食事を考える目安となります。
カロリー計算が自分では大変という方は、最近はカロリー計算を助けてくれるインターネットサイトやアプリなどもあるので活用してみると楽ですよ。
インスタントや加工食品は控える
カップ麺やレトルト食品などのインンスタント、加工食品、出来合いのお惣菜などはなるべく控えるようにしましょう。これらには添加物が豊富に入っているだけでなく、脂質や塩分、糖質なども高めで味が濃くなるようにつくられています。なるべくスーパーでカゴに入れる時には加工度の低いものを選ぶように心がけましょう。
アルコールは控える
アルコールは実は糖質が多く、太る原因となり、糖尿病の原因にもなるといわれています。特に避けたほうがよいのは、生ビール、日本酒、サワー、果実酒、梅酒、カクテルなどの甘い物です。これらは糖質が多めなので控えましょう。
逆にアルコールでも糖質が少なめといわれているのが、焼酎、赤ワイン、ウイスキー、ブランデーです。しかし糖質が低いからといって飲みすぎるのは肝臓にも負担になります。もし焼酎を飲むならば水割り、お湯割にするなど、飲みすぎない工夫をするようにしましょう。
甘いものや脂っこいものは控える
甘い物だけでなく脂っぽいもの、たんぱく質なども控えるようにといわれていましたが、最近は糖質を制限するだけでよいと言われています。しかし脂っこいものも糖尿病の患者さんは注意が必要です。
甘いものとしてはお菓子やケーキなどのスイーツなどはなるべく控えた方が良いでしょう。洋菓子よりは和菓子の方が血糖値を上げにくいと言われていますが、和菓子も糖質が多いので控えめに、たまにご褒美程度にしましょう。
また、脂っぽいものは血管合併症のリスクを減らすためにも摂取を控えたほうが良いと考えられています。脂質を取る場合には、オリーブオイル、えごま油、ココナッツオイルのような良質の油がおすすめです。
塩分は控え目にする
糖尿病と塩分は一見関係がないように思えますが、実は大いに関係があります。糖尿病の人は血圧の高い人が多いといわれていて、頻度は糖尿病でない人の2倍にのぼるといわれています。高血圧は糖尿病の合併症の発病・進行を早めるため減塩が大切です。糖尿病にまだなっていなくても高血圧を防止するためにも減塩を心がけましょう。
高血圧と一番深い関係にあるのは糖尿病性腎症という合併症です。塩分を摂りすぎると腎症の合併症を起こしやすくなるため減塩がすすめられます。目安としては、食塩1日7gが目安です。この目安はすでに糖尿病の人だけでなく、予防したい方にも同じことがすすめられます。
食物繊維を多く含むものを摂る
食事で食物繊維を多く摂取している人は、2型糖尿病のリスクが低く、体重も適正に管理できているという研究結果が報告されています。
食物繊維は、食べ物の吸収が穏やかにして血糖値を急激に上げにくいといわれています。また硬いものが多いのでゆっくり噛むことができて、早食い防止にもつながります。また、体内の余計なコレステロールを吸着して体外に出し、低下させる作用もあるため、血管合併症の予防や肥満解消にもつながるのです。
野菜類や海藻類には食物繊維が豊富です。お米をたべるなら白米より玄米や雑穀米がおすすめです。また、パンなどを食べるときは、全粒パンやライ麦パンなどを食べると血糖値の急上昇を抑えて、太りにくいともいわれています。
不飽和脂肪酸や大豆食品を摂る
不飽和脂肪酸を摂取すると、インスリン分泌やインスリン抵抗性が改善するという実験研究があり、魚の摂取による糖尿病のリスク低下が期待されています。特に小・中型魚および脂の多い魚の摂取により糖尿病リスクが低下したということです。例えばあじ・いわし、さんま・さば、うなぎなどがおすすめです。
またタンパク質を取るならば肉類などに偏らず、大豆食品もうまく取り入れましょう。豆類には糖質が少なくて、糖尿病の予防にもすでに糖尿病の方にもおすすめです。
また、厚生労働省の研究によると、大豆食品やイソフラボンを多くとっている女性では、2型糖尿病の発症リスクが低減するとする研究結果がでています。これは特に閉経後、または肥満女性に関しての傾向ということですが、大豆食品(豆腐、納豆など)を摂取することが糖尿病予防につながる可能性があるようです。
トクホ商品を取り入れる
血糖値が気になりだした方に役立つトクホ商品も様々に発売されています。トクホはうまく活用すれば糖尿病予防に効果的です。すでに糖尿病で治療を受けている方は、お薬の血糖値を下げる効果に影響する場合もあるので医師に相談するようにしてください。
例えば、難消化性デキストリンを含む「健茶王(カルピス)」、「グルコケア(大正製薬)」などがあります。これらは糖の吸収をおだやかにしてくれます。グァバ茶ポリフェノールを含む、「蕃爽麗茶(ヤクルト)」も血糖値の上昇を穏やかにしてくれるトクホ商品です。
しかしトクホを食べれば糖尿病にならないで済むわけではありません。あくまでも補助的なものとして使って、基本的な食生活をしっかりとバランスよく食べて、運動を心がけることが大切です。
予防に効果的な食品
緑黄色野菜
厚生労働省によると、野菜を1日に350g 以上、特に緑黄色野菜を120g以上摂ることが推奨されています。1日に食べる野菜のうち、3分の1を緑黄色野菜にするようにしましょう。食卓に並べた時に、様々な色がならんで色鮮やかになるのが理想的です。赤、黄色、白、紫、緑など色で食材を揃えるようにすると良いでしょう。
緑黄色野菜を食べると、植物性栄養成分(フィトケミカル)を十分に体に補給することができます。含まれるポリフェノール成分には、血管や細胞の老化防止の働きもあります。
例えばほうれん草、小松菜、ピーマン、アスパラなど緑色の野菜や、にんじん、パプリカ、かぼちゃのような黄色っぽい野菜が緑黄色野菜の代表です。しかしサラダにして生のままで食べようとするとボリュームが多く食べきれない方は、茹でたり蒸したりして火を通すとカサが減るのでたくさん食べられます。
きのこ類
きのこ類は糖質が少なく、食物繊維が多いので糖尿病の予防におすすめの食材です。糖尿病の食品交換表にもきのこ類は食べる量に制限はありませんと書いてあり、かさを増すために使うのにも便利な食材です。
スーパーには、しめじ、えのき、えりんぎ、まいたけ、なめこなどたくさんの種類のきのこが並んでいるので、毎日変えて取り入れてみましょう。また、複数のきのこを組み合わせて食べると美味しさもアップします。
魚類
魚を多く食べる男性ほど、糖尿病の発症リスクが下がるという研究報告がされています。魚類には必須脂肪酸が豊富に含まれていて、EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸は血糖コントロールに欠かすことができません。
肉類よりも健康的においしく満足できる主菜としては魚料理がおすすめです。蒸したり焼いたりとアレンジして日々の食事に取り入れていきましょう。
海藻類
海藻も特に制限なく食べてよい食品ということで、糖尿病の食品交換表でも薦められているものです。わかめ、もずく、ひじき、海苔、昆布など日本には様々な海藻類が豊富に存在しています。海藻類はほとんどカロリーがないので、カロリー制限したい方にもおすすめの食材です。お味噌汁やサラダなどにして頂きましょう。
野菜類
野菜には食物繊維が豊富で、血糖値の上昇をゆるやかにしてくれる作用があります。淡色野菜は両手いっぱいに乗るくらい、緑黄色野菜は片手いっぱいに乗る量を1日に食べると良いといわれています。毎食に穀物よりも野菜をたっぷりとる意識をもつようにしましょう。
特に食べる順番が大切で、野菜を一番最初に食べるようにするだけで血糖値が上がりにくくなると言われています。まずはじめに野菜から食べ、その後に肉、魚などのたんぱく類のおかず、最後にお米を食べるようにすると血糖値が急激に上がるのを抑えてくれるそうです。
大豆食品
大豆食品としては、豆腐、煮豆などを毎日食べると良いといわれています。大豆には糖質が少なく、糖尿病予防するときのタンパク源としておすすめです。大豆を含む豆類の摂取が耐糖能や糖尿病のリスクの低下と関連しているともいわれています。豆腐、揚げ、おから、 納豆、 湯葉など大豆食品はたくさんあるので、品を変えて毎日楽しみましょう。
玄米
日本人はつやつやの白米が大好きですが、この白米は実は栄養が抜けていて、血糖値も上げやすいので糖尿病予防にはあまりお勧めではありません。予防するならば、玄米がおすすめです。玄米は美味しくないイメージがあるかもしれませんが、最近は玄米を美味しくたける炊飯器などもあるので、ふっくらもちもちとした玄米を食べることができます。
玄米を食べると胃がもたれたり、逆に消化不良で便秘や下痢を起こす人もいるようなのでお腹の様子を見ながら取り入れていきましょう。食べる時にはよく噛むことがポイントです。
糖尿病の予防食レシピ
アクアパッツァ
いつの時期でも大抵手に入る白身魚とアサリを使ったアクアパッツァは主菜としておすすめです。オリーブオイルを油分として使うので、良質な脂質が効率よく摂取できます。
魚がメインなのでヘルシーな上に、一緒にきのこと緑黄色野菜のパプリカやトマトなどを加えたら立派な糖尿病予防メニューになります。大層なお鍋がなくてもフライパンで出来るので、気軽にチャレンジしてみてください。
ほうれん草のスパニッシュオムレツ
スパニッシュオムレツは余った野菜を使って卵さえあれば簡単にできてしまいます。卵を買いすぎた時にも便利で、たんぱく質豊富な主菜としておすすめです。中に入れる野菜は、ほうれん草やブロッコリーなどを使うと栄養的にもバランスがよくなります。
茹でておいた食材を小さくきって、卵と牛乳と混ぜ合わせ、お好みでチーズ、塩こしょうなどで味付けをしたら、フライパンで蓋をして焼きましょう。綺麗に切り分けると断面が綺麗なスパニッシュオムレツの完成です。
キャベツと厚揚げの味噌炒め
厚揚げを使ったメニューはボリュームもでて、満足感を得られやすいのでお肉の代わりにつかえて便利です。厚揚げは大豆製品なので糖尿病予防したい方にはぴったりの食材です。そのまま焼いて食べても美味しいですが、炒め物に使うのもおすすめです。
キャベツや、ピーマンなど冷蔵庫にある野菜と厚揚げを炒めて、味噌や豆板醤で少しピリ辛にすると美味しいですよ。ただし味付けは薄めにしましょう。コツはニンニクやショウガを効かせてアクセントをつけることです。美味しいのでついついご飯がすすんで食べ過ぎないようにしてくださいね。
まとめ
糖尿病の予防に役立つ情報をご紹介してきましたが、参考になりましたでしょうか?いままでの自分の生活スタイルを続けていると糖尿病まっしぐらかも!?と感じた方は、食事の内容の見直しや運動を心がけるなど、できることから始めてみてください。
もしも糖尿病になったら食事にもっと厳しい制限がつけられてしまいます。糖尿病にならないように予防をして、いつまでも健康で楽しく暮らせるように気をつけていきましょう。