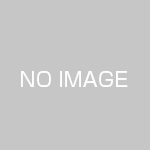山ガール入門!初心者のための登山準備から人気ブランドのおしゃれファッション!知っておきたい基本マナーを紹介
「森ガール」の次は「山ガール」!
たまには癒しを求めて自然に触れたいと簡単に考える人も、一度山で過ごす経験をすれば、街での時間と自然の中で過ごす時間では、その質が根本的に別物だと感じるかもしれません。
週末山に通うのにハマる女性たちが増えた理由は、日常の一部に、自然を取り入れてリラックスするというよりも、むしろ日常が自然の一部にあることに気付いてしまう、強烈な体験をするからではないでしょうか。
もともと女性は、旅行だったり美味しいものだったりと、体験を通して人生を楽しむのがとても上手です。そんな女性たちが山での豊かな体験にハマるのは必然です。ぜひこの記事で、山ガールになるためのきっかけを掴んでいただければ嬉しいです。
山ガールって何?
山ガールとは?
ファッショナブルなアウトドアウェアを着こなし、登山やハイキングにいそしむ女性たちを山ガールと呼びます。
山ガールの中にはほとんど山に登らず、街でアウトドアファッションを楽しむ人から、男性顔負けの本格的な登山をこなす人までレベルは様々ですが、「エコがおしゃれ」という見方の広まりと関連して、ファッションや音楽フェスから入る女性が多いようです。
週末になると高尾山などの近郊の山では、おしゃれで目を引くウェアやグッズを身にまとった女性同士の登山客で賑わっています。
いつから流行っているの?
2000年代前半には、3000m級の山麓で20代~30代の女性を見かけることは、生態系としてほとんどありませんでしたが、現在はかなり上級者向けの山にも山ガールは出没します。
以前は、中高年の男性の特権的な世界だった山に、女性が進出してきたのは2007年ごろから。このムーブメントは、第三次あるいは第四次登山ブームの一環だと言われています。
登山は、おしゃれでストレス解消に良いと気づいた若者たちが、どんどん登山にハマり、登山体験をシェアするようになったことから、敷居の高かった山がいっきに身近なモノになりました。
山ガールブームの火付け役として、雑誌やメディアの影響も大きいでしょう。2009年ごろから様々な媒体で「山ガール」特集が組まれ、2010年には、ユーキャン新語・流行語大賞候補にも選ばれています。
2012年からは「山ガールサミット」なるものも開催されていて、ブームの勢いを感じさせます。
山ガールファッション
山ガールといえば、カラフルで機能的なファッションが目につきます。それまで落ち着いた色合いの多かったアウトドアファッションですが、現在はとてもおしゃれなものが増え、ファッションから入る女性が多いのもうなずけます。
山ガールの激マストアイテムとなっている「山スカート」は、2006年ごろからモンベルが販売を開始したのが流行のきっかけです。山ですれ違う山ガールたちは、お互いのファッションをまず意識して親近感を覚えたり、可愛いと思ったものはさっそく購入して、次回の登山を楽しんだりと、ファッションでの楽しみの要素はとても大きなものなのです。
これを揃えればあなたも山ガール!
まずは登山靴を手に入れよう
最初に見たときは、登山靴のデザインに馴染みがなく、パッとしないと感じるかもしれませんが、ご安心ください。履いているうちに、あるいは他の人が履いているのを見るうちに、みるみるハマります。おしゃれなあなたなら、今までと同じようなデザインに見えていたものが、区別が細かくつくようになり、お気に入りのブランドがすぐにできるでしょう。
登山靴選びで気を付けたいことは、サイズが自分に合うものを選ぶこと。同じインチでもメーカーによってフィット感が全く違うので、実際履いて靴ひもを締めた状態で履き心地を確かめてみましょう。
特に足首のホールド感は、登山靴を選ぶ際の重要なポイントになります。フィットした登山靴は、足首にかかる負担を軽減してくれます。
登山靴は、ランニングシューズなどのスポーツシューズに比べて、クッション性に優れたものが多いです。やはり長い登山道では足に負担がかかるので、靴のサイズが合わなかったり、クッション性のないものを選んでしまうと事故の原因にもなりますので、多少値は張っても良いものを選びたいところです。
山ウェアを上手に選ぼう
山の天気は変わりやすく、環境変化にすぐに対応できる着こなしが必要です。外気温に触れると体温が影響を受けますし、急な雨などは、山ではよくあることなので防水の機能が必要です。また、寒い時には体温を逃がさない機能が必要ですし、暑い時には発汗性や体温調節を妨げないようなものを選びましょう。
防水・防風と保温や発汗による体温調整を両立する着こなしがレイヤリングです。レイヤリングでは、それぞれのレイヤーで機能の違うウェアを重ね着します。一般的なのが、3層の重ね着によるレイヤリングになりますので、レイヤーごとのウェアの選び方を紹介します。
レインウェア(アウターレイヤー)を選ぶ
一番外側のアウターレイヤーに着るウェアには、防水・防風・透湿性の機能が求められます。アウターレイヤーには、レインウェアやハードシェルなど防水性、撥水性のある素材のウェアを選びましょう。軽くて防水性があり、蒸れないゴアテックスのような素材の高機能ウェアがたくさん出ています。
アウターレイヤーは、最も人目につくウェアになりますので、できれば見た目にもこだわりたいですね。幸い女性用のレインウェアは、驚くほどかわいいものがたくさんあり、迷ってしまうほどです。
ポンチョ型のものや色合いが素敵なものなど、街で出かけるときに着ても遜色ないものですので、機能性とデザインでお気に入りの一点を選びましょう。
薄手のフリースジャケット(ミドルレイヤー)選ぶ
ミドルレイヤーは、薄手のフリースジャケットのような、保温性や吸汗速乾性に優れた防寒ウェアを選びましょう。アウトドアの世界ではフリースウェアもかなり進化しています。
マイクロフリース素材は、毛玉ができにくく、きめ細やかなフリース素材で肌触りも抜群ですし、バイオミミクリフリースなどの保温性を追求した素材もあります。
山ウェアやグッズは、執着せずにはいられない要素がたくさんありますので、素材好き女子には、山に行く前から楽しみがたくさんあります。
化学繊維やウールのカットソー(ベースレイヤー)を選ぶ
インナーに着るベースレイヤーは、肌を快適な乾いた状態に保つ素材のものを選びましょう。近年人気なのは、メリノウールという速乾性と防臭作用に優れた素材です。汗をかくと、冷えたときの不快感はなんともいえませんが、メリノウールならこの不快感がほとんどありません。
同じようにポリエステルの中でも、汗に含まれるアンモニアを分解してくれる素材など、優れ素材が多くありますので、ベースレイヤーのウェアは、肌触りと素材で選ぶことをお勧めします。
万が一に備えて、薄手の中綿ジャケット
ミドルウェアは一枚だけとは限りません。体温調節をするために急な冷え込みに備えて、軽量で圧縮性のある、薄手の中綿ジャケットやダウンベストなどを用意すると良いでしょう。コンパクトに収納できるものであれば、ザックの場所もとらず持ち運びに便利なので、常に一着備えておくのが一般的なスタイルです。
動きやすさ重視ならスカートやボトムにレギンスを
山ガールといえば、山スカートにレギンズという、おしゃれで憧れるスタイルです。女の子らしさも相まって、またたくまに広がった山ガールスタイルは、ファッション性だけじゃなく運動性が高いことが特徴です。
動きやすさ重視の方はもちろん、ファッション性はゆずれないという人でも、山スカートとレギンスを何着かは揃えておきたいところです。
その他あると便利なアイテム
それ以外にも、日差しから肌や目を守る帽子やサングラスなどはあると便利でしょう。登山用ザックやサブポーチなども使いやすいものを見つけましょう。荷物に余裕があれば、小川などで足を休めるためにサンダルを持参される人も多いです。
アウトドアウェアは、小物が充実していますので、ベテラン山ガールのザックの中身を参考にさせてもらい、徐々に便利グッズを増やしていきましょう。
人気の山ガールブランド
L.L.Bean
アウトドアウェアの老舗ブランド「L.L.Bean」は、100年以上に渡ってキャンパーやハイカーに愛され、信頼を蓄積してきました。山ガールのみならず、子どもからお年寄りまで、ひときわセンスの光るウェアを着ているのを見かけます。
ぱっとみただけで「L.L.Bean」だとわかるほどの定番で、温かみのあるデザインと色合いが、アウトドアの醍醐味とマッチしています。
着るのは街ででも良いですが、「L.L.Bean」のウェアが真価を発揮するのはやはりフィールドです。「L.L.Bean」に身を包んで山に出かけてみてはいかがでしょう。
Columbia
「Columbia」といえば、ウインタースポーツのブランドだと認識している人が多いと思います。冬山は一年の中で最も過酷で、これを制することができれば他にも通用します。
「Columbia」の実力は、ジャケットが証明しています。アウターとインナーをジッパーで接合できる3ウェイ設計の「インターチェンジシステム」を採用したジャケットは、汎用性が高く、シーズンをまたいで着用することができるので、1着持っていると重宝します。
機能面だけではなく、おしゃれ系の古着屋に置いてあってもおかしくないデザインは、「Columbia」の確実な強みです。靴、ザック、ジャケット、どれをとっても身に付けているだけで、ハイセンスを感じさせます。
THE NORTH FACE
お手頃な価格で購入できる「THE NORTH FACE」は、アウトドアショップやアウトレットショップなど至る所で目にします。プロダクト数も多く、ファンも多いので、ザックがお揃いということがよくあるそうです。そういった場合は、親近感が断然高まること必至です。
身近でフレンドリーなのが「THE NORTH FACE」の良いところです。山で「THE NORTH FACE」から始まる輪を広げるのもいいですね。
Foxfire
フライフィッシングのベストから始まったアメリカは、ジョージア州出身の「Foxfire」をご存知でしょう?「Foxfire」が大事にしているのは、「自然との融和」と「自然との共生」。遊び心があり、自由なデザインは、それを着こなす山ガールの性格を表しています。着ているモノは着ている人の思想を反映します。
もちろん品質も妥協したくない人向けのウェアも多くあります。「Foxfire」の技術の結晶ともいえる「アイスフィールドジャケット&パンツ」は、玄人ファンも掴んで離さない魅力を秘めています。本物志向のウェアで、山ガールとしてのレベルアップを見据えているなら、「Foxfire」のウェアはうってつけだと言えるでしょう。
HELLY HANSEN
北欧生まれのアウトドアブランド「HELLY HANSEN」は、防寒性に優れた山ウェアを販売しています。機能性もさることながら、そのデザインは、シンプルで洗練された、北欧らしいおしゃれ感を醸し出しています。
落ち着いた大人の着こなしがお望みなら、迷わず「HELLY HANSEN」を選びましょう。耐久性もありますので、飽きがこず長く使い続けられることでしょう。
登山用ザックのメリットと選び方
メリット1:背負いやすく疲れにくい
ウェアと同じように、登山用ザックは驚くほど機能性に優れています。長時間、何キロもある荷物を背負っても疲れにくい設計になっており、フィット感があってとても背負いやすいです。ただし、サイズを間違えると、荷物が重く感じて無駄に疲れたり、あちこち痛くなってしまうので、店舗に直接出向いて背負ってみることが必須です。
登山用ザックがフィットしているかどうかは、とても重要なポイントです。肩にかけるベルトだけじゃなく、胸の前や腰の部分にもベルトがあるものがあり、サイズがピッタリならうまく重さを分散してくれるので、登山用ザックを選ぶ際は、店員さんにベルトの長さの調整方法を確認してサイズ確認をしておきましょう。
メリット2:耐久性が高い
登山用バックは、かなり重い荷物を入れるので、耐久性に優れた素材でできています。最近では、軽量の傾向にどんどん進化し、とても軽くて破れにくいザックに感動すら覚えるのではないでしょうか。見た目もおしゃれなものが多いので、登山ザックを普段使いにする山ガールが多いのも納得できます。
名の知れたブランドのものは安心して使えますので、何泊もするようなハードな山登りを考えていな限り、耐久性に関してはどれを選んでも間違いないと思います。中級者以上になってくると、軽量性が耐久性の犠牲になっているものもあるので、どっぷり山にハマれば、どちらかを選ぶ場面も出てくるかもしれません。
メリット3:便利機能がたくさんある
登山用ザックは、背負いやすさや耐久性以外にも便利な機能がたくさんあり、その機能を知るだけで楽しくなります。まずはポケットがたくさんあり、だいたいの登山用ザックは、ペットボトルなどを入れるためのポケットが外側についています。
また、内側にも区切りがあり、小物が入れやすいものや、容量によってはザックのサイズが変化するもの、雨が降った時用に口の部分にカバーがついているものなどがあり、とても機能的に考えられています。
機能を知れば知るほど、登山用ザック選びに迷ってしまうかもしれませんが、どれを選んだとしても使っているうちに愛着が湧いてきますよ。
日帰り登山なら15~25Lのザック
登山用ザックを選ぶ際、迷うのはザックの容量ではないでしょうか。日帰りの装備なら15~25Lでほぼ収まります。必要以上に大きなものを購入すると、無駄に重い荷物を背負うことになるので、日帰りメインで考えている人は、デイパック型のザックを購入しましょう。ハイキングなどで、よく見かけるのがこのサイズのものです。
泊まり登山なら30~40Lのザック
富士山などの高山や長距離の縦走登山、荷物の多いキャンプでは30~40Lのザックが必要になります。このサイズでも十分にコンパクトなものがあるので、本格的に登山を考えている人は、こちらのサイズで購入しておくのが良いでしょう。
テントを持ち運ぶことを考えている人は、さらにこの上のサイズ(60L以上)が必要になり、こうなると、見た目にも結構大きなものになりますのでご注意ください。
初心者山ガール向け!正しい歩き方
登山口で準備運動
登山の前の準備運動は、けが予防や疲れの軽減のためにとても大事です。日頃から登り慣れてない人は、特にこれから動かす筋肉をよくストレッチしておきましょう。ストレッチを行うかどうかで、翌日の筋肉痛の度合いが変わってきます。できれば、10~15分ほどかけて筋肉を伸ばしましょう。
アキレスけんを伸ばしたり、足首を回したりといった足首周り、太ももの前や太もも後ろからお尻にかけては、特に大事ですが、重いザックを背負って長距離を歩くため、体幹や背中なども入念にストレッチしたいところです。伸ばすだけじゃなく、軽く動かして「今から登るよ」と筋肉に伝えるように、心の準備も行いましょう。
体の準備が整ったら、ザックや靴がフィットしているか、ベルトや靴ひもをチェックしましょう。ちょっとしたことで楽に登ることができるので、ゆるみに気付いたら、ベルトや靴紐を締め直すことを怠らないようにしましょう。
上りの基本姿勢
何も考えずに、いきなり登り始めてしまうとすぐに疲れてしまい、悪い時には体を痛めてしまいます。上る前に登山での基本姿勢を確認しておきましょう。
まずは、上りの基本姿勢ですが、頭や背中、腰、後ろの脚が一直線になるような体の軸を作ります。階段を上るときのように、膝を高く持ち上げた状態です。残った後ろの脚で体重を支えるので、バランスが大事になります。
前の脚が着地したら、重心を移動させながら後ろ脚を前に出していきますが、このときも体の軸を意識しましょう。前に倒れこむように重心移動ができれば、より楽に歩くことができます。
体が一直線になることで、余分な筋力を使わずに、骨で体を支えながら上っていくことができるので疲れにくいです。体が直線のまま重心は前に移動しますので、猫背になったり腰が曲がらないようにしましょう
足ですが、つま先を少し外に向けて股気味で歩き、足首の負担を軽減してください。斜面が大きいほど角度をつけます。
着地をするときは足の裏全体をべったりつけます。かかとやつま先から着地してしまうと関節に負担がかかります。普段と違う歩き方なので慣れるまでは少し難しいと感じるかもしれませんが、登山に適した歩き方なので体が覚えてしまえば楽になります。
下りの基本姿勢
下りの姿勢も基本は上るときと同じです。体の軸に一直線の線を作って、重心を移動させながら下ります。足首は、つま先を外に向ける必要はなく自然に歩きましょう。
重心の移動が急だと、膝を痛める原因になりますので、後ろ脚になるべく重心を残したまま、そっと着地し、膝を柔らかく使って、クッションの役割を持たせると良いです。
下りるときに初心者がやりがちなのが、恐怖心から腰が引けてしまうことです。こうなると、重心の移動が上手くいかず、脚や腰にも負担がかかってしまうので、後傾にならないように、あくまで体の軸を意識した歩き方をキープします。斜面の角度が急な場合は、腰を落としてやや前かがみになり、体の線を地面と垂直にして対処しましょう。
膝や腰の負担が心配な人は、ストックを使うと軽減されます。
呼吸法を意識する
空気が地上より薄い山では、たくさんの空気を肺に取り入れる呼吸法が大事になります。長い距離を登り続けるために、3,000m超の山で高山病にならないように、登山での呼吸法を覚えておく必要があります。
基本の呼吸は、鼻から吸い口から吐くものです。体の動きに合わせたリズムで呼吸することが大切なので、自然に呼吸も短くなります。口から吐くときは、短く強く「フッ」と吐き切るようにすると良いです。
また、吸うときも吐くときも、短いリズムでは十分に空気が入らないと感じたら、2回吸う、あるいは2回吐くなどで、肺の中に空気が残らないようにすると効率的に酸素が取り込めます。
鼻から息を吸うことでフィルターがかかるので、高所の乾燥や寒冷から身を守ることになります。それでも気分が悪くなってしまったら、休憩して早くて短い呼吸から、ゆっくり大きく息を吸い込む呼吸を5~6回繰り返し、血中の酸素濃度を高めます。
小股で歩くようにする
歩き始めるときは、1分くらいはゆっくりめにスタートします。早く登ろうとせず、なるべく楽なペースで登ることが持続にはとても大切です。このとき自分の靴の長さから、その2倍までの小股で歩を進めるように意識をしましょう。
小さな歩幅で歩くことで、基本姿勢が崩れることなく歩けます。また、歩数が多いぶん体重の負荷を分散できて、足への負担を軽減できます。
疲れたら早めに休憩を取りましょう。しかし、長く休みすぎると、歩き始めたときに負担が大きくなってしまうので、5分くらい立ったままでの小休憩を頻繁に取るようにします。1時間ほど歩いたら荷物を降ろして15分くらい休むなど、ペースを工夫しましょう。
段差を避ける
階段状の場所では無理をせず、なるべく段差を避けて小股を維持します。段差を避けることで、足への負担を軽減して、必要以上に酸素を消費しないで済みます。
太ももの筋肉をがっつり使うような動きをすることで、酸素の消費量がぐっと上がっていまい、ペースが乱れます。なるべく大きな筋肉を使わない、段差の低いコースをとって斜めに歩いたり、S字で登るような工夫が大切です。
知っておきたい登山マナー
公共交通機関でのマナー
登山は、ただ山に行って登るというシンプルなレジャーですが、安全にそしてお互いが快適に登るための暗黙のルールがいくつかあります。登山初心者の人は、山のルールを知らなずに登ってくる人もいますが、自然を共有する共同体意識を持つためにも、基本的なルールだけでも知っておくべきでしょう。
まず道中ですが、山の荷物は大きくて場所をとるので、込んでいるときは、座席の上の荷物棚を使うのは遠慮して足元に荷物を置きましょう。
浮足立って、周りが見えなくなる人もいますが、公共交通機関を利用しているのは、登山者だけではないので、周りへの配慮を忘れずにしましょう。グループでまとまって、出入りの邪魔にならないところに立ち、背中側のスペースも気にしておきましょう。
登山中はあいさつを大事に
登山をすると、街にはない気持ちの良いコミュニケーションに驚く人もいます。山では、すれ違った人とあいさつするのが文化ですので、恥ずかしがらずに「こんにちは」「お先に」などと声をかけましょう。
山でのあいさつにもルールがあり、基本的には上る人から声をかけることになっています。下りの人は、相手から声をかけられるのを待ってあいさつをしましょう。中には、あいさつができないほど体力を消耗していたり、あいさつの文化を煩わしく感じる人もいますので、あいさつがない場合や大人数の場合は、軽く会釈をしてすれ違いましょう。
山中では、同じ人に何度も出くわすことがよくあるので、自分を覚えてもらう意味でもあいさつをしておくと、会話のきっかけになります。会話は大事な情報を得られる機会にもなり、大きな事故を防ぐためにも大切です。
また、こうした山での出会いは登山体験に印象を与えたり、その後の思わぬ交友関係につながることもありますのであいさつを大事にしましょう。
上りの人が優先
山では上りの人が優先という暗黙のルールがあります。下りの人は、前から来る人に気付きやすいので、すれ違う場所も見つけやすいです。登山道は、道幅が狭いところがあり、すれ違うのが難しいところも多いです。安全にすれ違うためにもルールを守ることが大切です。
ただ、上っているときに、相手が避けないからといって腹を立てるのはトラブルのもとです。臨機応変に対応することが、ルールを守ること以上に大切であることも覚えておきましょう。
例えば、狭い山道で、安全にすれ違える場所が上りの人に近かったとしたら、上りの人でも相手に道を譲るべきですし、団体は少ない人数のグループを先に通すこともあります。危険もあり体力の消耗も平地とは違う山中では、融通を効かせた対応と譲り合いの心を持ちましょう。
周りをよく見て行動する
上りのときは、自分の足元ばかりに目が行きがちです。気付いたら同行者を見失ってしまったり、落石に気付か中ったりと、自分やほかの人への危険にもつながりますので、できるだけ周りを見て行動すること心掛けましょう。
また、山では解放感から、つい周りが見えなくなることがあります。大人数で騒いでしまうと、自然を堪能しに来た他の登山者に迷惑がかかりますので注意が必要です。
出たごみは持ち帰る
ほとんどの山にはごみ箱がありません。ごみが出たら、処分して荷物を軽くしたいと考える人もいますが、自分の出したごみは、全て自分で持ち帰るのが基本です。山小屋などでは、売店で買ったものから出たごみのみ山小屋で回収してくれます。
コンビニや駅でごみを処分するを見かけますが、登山者のマナーが疑われて迷惑がかかりますので、必ず家まで持ち帰って処分しましょう。せっかく自然の中に来ているのですから、マイ箸やマイ食器を持参するなど、ゴミが出ないような自然への配慮も持ちたいです。
植物等の採集・野生動物への餌付け禁止
山には普段目にしない動植物がたくさんあります。これも登山の楽しみの一つですが、むやみに採取したり、餌付けしたりするのは基本的に禁止です。生態系保全のために、その場で見て楽しむか写真を撮って楽しむくらいにとどめておきましょう。
野生の動物であれば、人に慣れることで、警戒心が薄れて持物を取られたり、近づきすぎることで起こる事故などがありますので、いくら可愛くても距離を持って楽しむことが大事です。
山でのトイレ
女性が山に行って困るのがトイレではないでしょうか。登山客の多いハイキングコースでは、登山口や休憩スポットなどに、トイレがいくつか設置されているところがありますので、事前にトイレの下調べしておきましょう。
街中と違って水洗ではなく、頻繁に清掃されるわけでもないので、できるだけきれいに利用して、次の人にも気持ちよく使ってもらうことがマナーです。
どうしてものときは、山中で用を足す必要も出てくるかもしれません。そんなときのために、携帯トイレやティッシュを用意しておくと、自然を汚すこがなく、安心できます。いざというときの備えをしておきましょう。
先輩山ガールをお手本に
山ガールスナップ
山ガールファッションを揃えたものの、センスが間違っていたり、ちぐはぐだったりするのは恥ずかしいですよね。山ガールのコーディネートは、みんな個性的で基本的に間違いはありませんが、参考になるものがあるとアレンジが効くと思いますので、センスの光る先輩山ガールのコーディネートが参考になるのではないでしょうか。
山ガール雑誌
先輩山ガールの装備やおすすめ登山コース、山での過ごし方などの突っ込んだ情報が知りたい場合は、山ガール雑誌が良いでしょう。とても有名なものには山ガール元年2009年に創刊し、山ガールブーム最先端の情報を発信し続けている「ランドネ」(えい出版)があります。
また、登山雑誌の雄、山と渓谷社が出版する女性のためのアウトドア情報誌「Hutte(ヒュッテ)」には、ファッションから山歩き術まで内容の濃い情報が入手できます。おしゃれ系アウトドア情報誌「BE-PAL(ビーパル)」の増刊号として、女性向けに出版されている「falo(ファーロ)」にも、ファッションやメイク、山レシピなど欲しい情報が手に入ります。
人気ブログ
山ガールの生の声や体験記はとてもリアルで、山ライフの参考になるとともに、モチベーションも上げてくれるので、お気に入りの先輩山ガールのブログを、定期的にチェックすることをお勧めします。山ガールブロガーなおさんのブログ、「みんな空の下」は、写真やルート情報などを細かく載せていて、読むだけで自分が登った気になります。
「週末★山ガール」のWACOさんは、登山をたしなむ人なら誰もが行ってみたい山々の登山記を載せていて、山ガールのネクストステップを示してくれます。山へ行くと、シェアしたくなり、他の人の情報がとても役に立つので、山ガール入門としては、まずブログを読んでみるのが良いと思います。
まとめ
これだ!という最初に登る山を決めておき、準備にとりかかると、山ガールになるのも早いでしょう。登り始める前には、靴やウェア、ザックを合わせて平地で予行演習をしておくのが良いでしょう。
ひとたび山に登りだすと、ネットやSNSでの有益な情報をキャッチするコツがつかめると思いますし、すぐに仲間ができると思います。。山ガールライフの一歩を踏み出して、Facebookのタイムラインを山一色にしてみるのも楽しいでしょう。
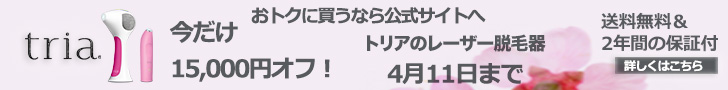















![[ゴーライト] GOLITE Rush 20L Pack (Unisex) M/L size](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41zEf99P3hL.jpg)



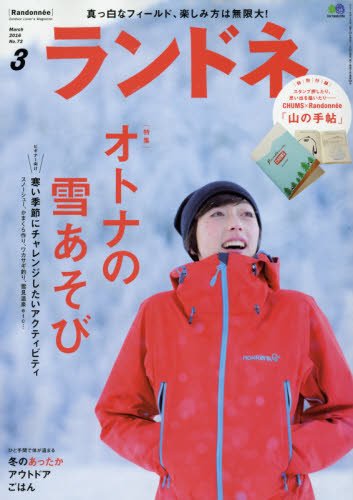
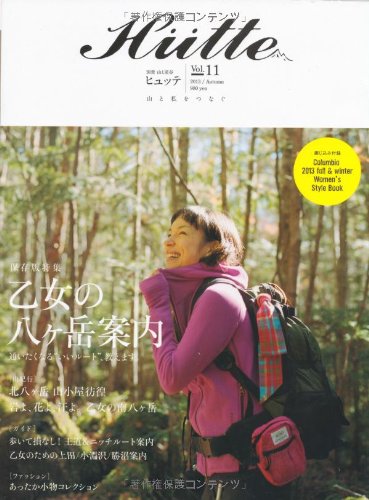
![falo (ファーロ) BE-PAL for natural outdoorgirls 10 2013年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51b5W--ugJL.jpg)