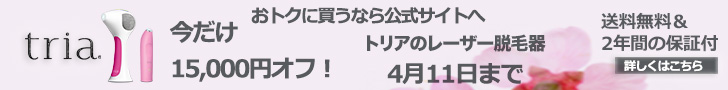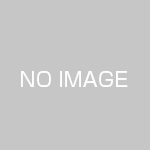頭頂部に痛みが!これってもしかして病気なの?9つの原因と考えられる6つの病気の可能性について徹底紹介!
頭頂部が痛い原因とは?
血行不良
脳は体の司令塔にあたる部分でとても大事なことは言うまでもありません。その脳への血流が足りない場合、もしくは急激に血行がよくなった場合に頭痛となって表れます。
肩コリ・首コリ
当たり前ですが、頭は心臓よりも上に位置しています。つまり、重力に逆らって血液を脳に送っていることになる訳です。その通り道である血管が、首や肩の筋肉のコリによって圧迫されることで頭痛が出てしまいます。
気圧の変化
天気が悪くなったり、台風が来たり、梅雨時になると頭痛が出るというケースです。気圧が下がると、空気中の酸素濃度が低くなるために、それを補うために脳への血流が増えて頭痛が出ます。
冷え
気温が低かったり、冷たい食べ物や飲み物で体を冷やしたりすると、筋肉が緊張したり、体全体の血液に循環が悪くなったりして、結果として頭痛に至るケースがあります
生理
女性の場合は、生理中の血流の変化や、ホルモンバランスの変化により、自律神経の働きにアンバランスを生じることで頭痛が出るケースがあります。
傷病性のもの
打撲などの外傷や、脳梗塞、脳内出血などをはじめとする脳の疾患による場合です。
皮膚の疾患
皮膚に炎症を起こしていたり、腫れ物や吹き出物ができている場合に、痛みとなって表れる場合があります。
高血圧
血圧が高いと強い力で血液を送り出すことになるので、血管壁にかかる負担が増し、脳梗塞や脳出血のリスクが高くなります。
二日酔い
アルコールを分解する時にアセトアルデヒドという物質が分泌され、飲酒中の排尿に伴ってその血中濃度が高くなってくると頭痛となって現れます。
頭頂部の痛みがあるときに考えられる病気や疾患とは?
頭痛って本当につらいですよね。ズキズキと脈打つような痛みであったり、頭を締め付けられるような痛みであったり。また、痛みの出る場所もさまざまですが、今回は特に頭頂部とその周辺の痛みに関してとりあげてみたいと思います。
頭痛に関しては、病院で検査をしても実にその内の80%が原因不明と言われるそうです。病院に行くほどの症状なのか、それともすぐに行った方がいいのかの判断に迷われたら参考にしてみてくださいね。
偏頭痛
偏頭痛とは、なんらかの原因によって脳の血管が急激に拡張して起こるタイプの頭痛のことです。血液の循環がよくなることはいいことのように思えますが、急な変化に伴って頭痛も出てしまいます。
血液の循環に関することなので、高血圧はもちろんのこと、低血圧の人にも起こりえます。また。ホルモンバランスも影響することから、生理中に偏頭痛が出るという人もいます。
偏頭痛には前兆のあるものとないものと前兆があるものの2つのタイプがあります。頭のどちらか一方のサイドに起こることが多いですが、頭頂部に痛みが表れることもあります。
はっきりとした原因はいまだに分かっていませんが、ストレスや空腹、寝不足や過労、ホルモンバランスの変化などがその要因ではないかと言われています。
前兆がある偏頭痛の場合は、閃輝暗転といって目の前にぎざぎざとした光が閃いたあとに視界が暗くなるものや、視野の半分がかけて見えたりといったことが起こったあとに頭痛が出ます。
前兆のない偏頭痛の場合は、ズキズキと脈打つような痛みが半日から3日の間続きます。急に立ち上がるなどの動作をしたすると痛みが増したり、吐き気がしたりします。また、光の刺激などで痛みが増強されることもあります。
緊張型頭痛
頭痛の中でも最も多く見られるのがこの疾患です。偏頭痛のズキンズキンと脈打つような痛みと違って、頭全体が締め付けられるような、圧迫感のある頭痛がするのが緊張型頭痛の特徴です。タイプとしては、反復性の緊張型頭痛と、慢性の緊張型頭痛の2つがあります。
緊張型頭痛の場合は、偏頭痛のような視野に影響が出たり前駆症状があることはまれで、症状としては軽度~中程度なので、日常生活に支障をきたすほどではありません。一日の中で見てみると、夕方頃に倦怠感や目の疲れを伴って出ることが多いようです。
反復性の緊張型頭痛とは、デスクワークや、パソコン・スマホなどの見すぎによる首や肩のコリから起こることが多いです。多くの方が頭痛とともに首や肩の筋張を訴えます。
慢性の緊張型頭痛は、首や肩の筋張はもちろん、精神的なストレスなどが原因で、脳が痛みに過敏になっている状態の人に起こりやすいようです。
副鼻腔炎
副鼻腔炎とは、細菌やウィルスに感染することにより、副鼻腔に炎症が起きる疾患で、鼻水や鼻づまりなどのほかに、頭痛が出ることも知られています。
急性の副鼻腔炎が治りきらずに慢性の副鼻腔炎に移行するケースがあります。また、気管支喘息に伴う慢性の副鼻腔炎もあり、こちらの方は治りにくい症例とされています。
群発頭痛
群発頭痛はあらゆる頭痛の中で最も痛みが強い頭痛だといわれています。偏頭痛に比べるとその発症率は100分の1ほどで、あまり知られていない頭痛といえるかもしれません。
偏頭痛が女性に多く見られるのに対して、群発頭痛は男性の方に多くみられ、夜寝てからしばらくして、眼窩の奥や、側頭部を中心に痛みが出るのが特徴です。
欧米では自殺頭痛などという物騒な名前付いている通り、発作中は痛みのためにじっとしていられず、のたうちまわったり壁を叩いたりして骨折にいたるケースも見られるほどです。
くも膜下出血
上記の頭痛は直接命に関わることは少ないですが、脳卒中によって起こる頭痛、特にくも膜下出血の場合は直ちに命に関わりますので注意が必要です。
この頭痛の特徴は症状が突然現れることです。頭を何かで殴打されたような痛み方や、頭が何かにぶつかったかのような痛みの始まり方をします。
たいていの場合は、脳の動脈瘤が破裂して起こります。痛みの起点がはっきりしていて、偏頭痛のように段々痛くなるのではなく、ほんの数十秒の間に痛みがピークの状態でやってきます。多くのケースで吐き気や嘔吐をともないます。
痛み方としては「今までに感じたことのない痛み」というのが特徴で、失神などの意識障害を伴うケースも多々見られます。頭痛が軽い場合には見落とされがちな疾患なので、頭痛持ちの人は一度は検査してもらうことをおすすめします。
あなたの頭痛はどのタイプ?
ひとくちに頭痛といっても出る場所や痛みの種類はさまざまですよね。ここでは痛みの出方や、出る場所をタイプ別に見ていきたいと思います。自己判断は禁物ですが、参考程度にはなると思います。
ズキズキ痛む場合
偏頭痛、もしくは三叉神経痛や後頭神経痛などの疑いがあります。
ピリピリ痛む場合
後籐神経痛(頭皮神経痛)の可能性があります。
頭皮に腫れがあったり触る・押すと痛い場合
外傷や神経痛の可能性があります。
左側、もしくは右側だけ傷む場合
偏頭痛や群発頭痛、脳卒中の可能性があります。
頭頂部に痛みがあるときの治療法と対策
患部を冷やす
頭痛の多くが血液量が増したときに起こるので、冷やすことで血管の拡張を防ぎ、血液の循環を抑制することにより痛みを緩和します。入浴は逆効果になるので控えた方がよいようです。
濡らして絞ったタオルを冷蔵庫で冷やしたものを用いたり、保冷材などを薄手のタオルなどで包んだものなどで、痛みのある場所を直接冷やします。静かな環境でやるとよいようです。
ストレッチ
緊張型頭痛の場合、同じ姿勢で仕事を長時間続けることにより、筋肉が硬くなって血行が悪くなることにより痛みが増してしまうので、ストレッチングで筋肉を柔らかくするのが効果的です。
両肩を上げてストンと落とす動作を、気が付いた時に10回~20回行なったり、首を片側にゆっくりと傾けて首の横側の筋肉を伸ばしたり、椅子に浅く腰掛けて前屈をするなどすると効果的です。
カフェインを摂取する
カフェインには交感神経を刺激して、血管を収縮させる効果があります。コーヒー、紅茶、日本茶などを薄めにして飲むと、頭痛の初期には効果があります。ただし、飲みぎると逆に頭痛の原因ともなりかねないので注意が必要です。
投薬治療
偏頭痛の治療は薬を用いるのが一般的です。トリプタン系薬剤やエルゴタミン製剤が用いられることが多いようです。ただし、予防については薬に頼るのではなく、生活習慣の見直しも大事です。
市販薬にも頭痛を抑えるものがありますが、飲みすぎてしまうと、薬の効果が切れるたびに頭痛が起きてしまい、また薬を飲むという悪循環に陥る薬剤誘発性頭痛になってしまうこともありますので注意が必要なようです。
頭頂部に痛みがあるときは何科に行くべき?
神経内科
神経内科は、内科のなかでも特に脳神経系を専門にしている部門です。神経痛や、脳や脊髄、神経、筋肉の病気を診てくれます。通常の頭痛の場合はまずここに行くのがよいようです。
脳外科
脳外科では、脳卒中やくも膜下出血などの脳の病気全般を対象に、外科的な処置をしてくれる部門です。明らかな疾患が認められた場合はこちらを受診するのが良いようです。
まとめ
今回は頭頂部の痛みについてお話してきましたが、頭痛の原因のほとんどに血液が関与していたことが分かって頂けたのではないかと思います。
血管拡張性にしろ収縮性にしろ、急激に変化が起こることにより頭痛につながってしまいますので、日頃から生活習慣や食習慣に気をつけて、頭痛がそもそもでない体質にしていきたいですね。